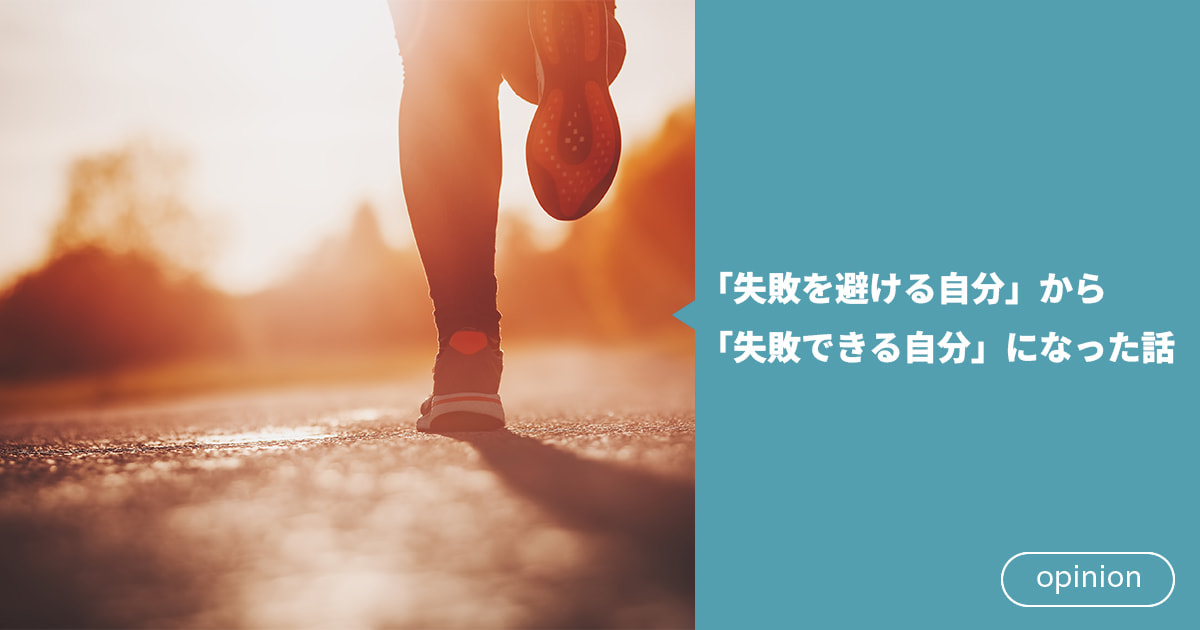これが私なりの「言葉と、生きていく」
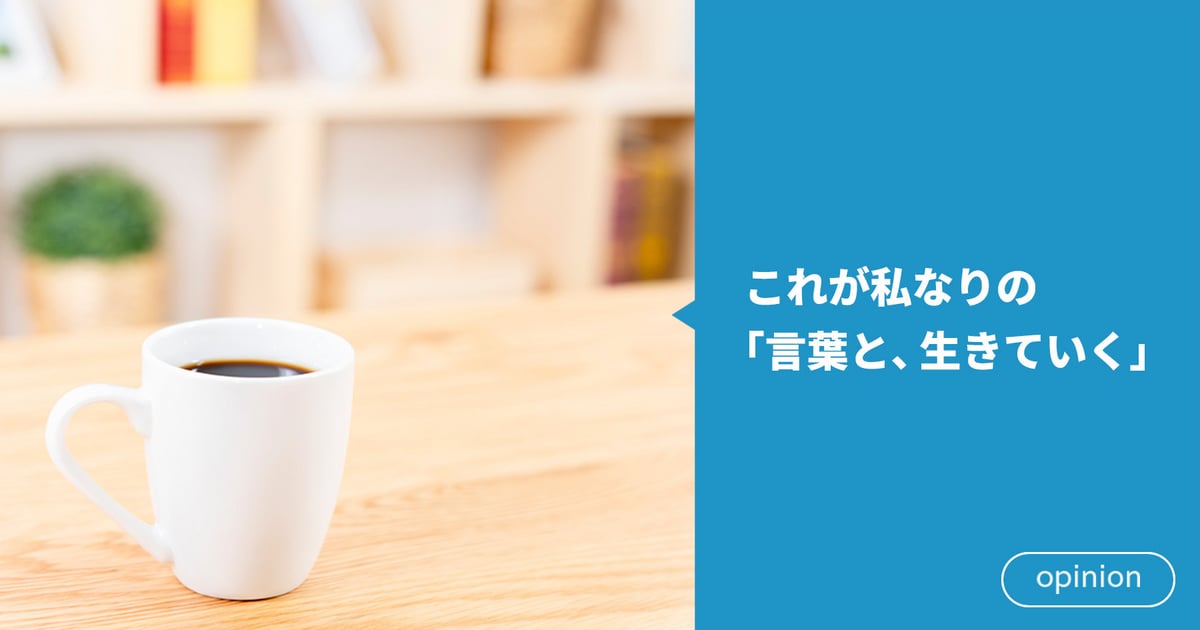
「お前んとこのCM、良いよな。あの『言葉と、生きていく』ってやつ」
先日、中学校からの友人に会った際、こう声を掛けられ、ビックリしました。
まさか、この友人の口から聖教新聞のキャッチコピーが飛び出すとは。趣味は御朱印集めで、中国や韓国に対して少し偏見があり、保守的な言動の政治家を好むという、私とは考え方が全然違うのにもかかわらず、なぜか仲が良い、いわば〝腐れ縁〟に近い友人です。
CMは、男の子が入院中の祖母のためにオリジナルのラジオ番組を作り、励ましの声を届けるという内容でした。ぜひご覧ください。
その友人は、たまたまCMを目にして、何となく「いいじゃん」と思っただけかもしれません。それでも私は、彼が創価学会の本質を分かってくれたと感じました。
「言葉と、生きていく」はさまざま解釈が可能ですが、このCMの趣旨は「大切な人へ、言葉を通じてエールを贈る」こと。まさに創価学会の活動を象徴していると思うのです。
私たち創価学会員は、苦しい時や自分を奮い立たせたい時、日蓮大聖人が信仰のあり方を説いた論文や門下を励ますために送った手紙などを集めた聖典「御書」を学んだり、御書に基づいた池田大作先生のご指導を紹介したりして、自他にエールを贈っています。実は私自身も、御書によって救われた経験があります。
コロナ禍のマタニティライフ
今から5年前、結婚して間もなく、妻が妊娠し、私たち夫婦は穏やかに赤ちゃんを迎えるための準備期間を過ごすことを思い描きました。しかし、そこへ突然のコロナ禍が影を落としたのです。当時、まだウイルスの全容がわかっていなかったため、妻は、〝もし感染したら、おなかの子はどうなってしまうのか〟と不安で押しつぶされそうになり、神経をすり減らしていきました。
ついには、不眠に陥った妻は服薬が必要に。医師からおなかの子への影響について、「全くないとは言い切れない」と告げられ、妻は不安そうに涙を流しました。「大丈夫だよ」と声をかけましたが、私の言葉は妻の深い苦しみに届かないように見えました。計り知れない苦しみを抱える妻を目の当たりにし、私自身も人生で最も辛い時期を過ごしました。
ある真夜中、ふと目を覚ますと、暗闇の中、妻が震える体で必死に題目を唱えている姿がありました。その姿に、どうしようもないもどかしさと深い悲しみを感じました。
私に一体何ができるのか――離れて暮らす母と電話した際、教えてもらったのが、次の御書の一節でした。
我ならびに我が弟子、諸難ありとも疑う心なくば、自然に仏界にいたるべし。天の加護なきことを疑わざれ。現世の安穏ならざることをなげかざれ。我が弟子に朝夕教えしかども、疑いをおこして皆すてけん。つたなき者のならいは、約束せし事をまことの時はわするるなるべし。
(開目抄、新117・全234)
意味
私ならびに私の弟子は、諸難があっても、疑う心がなければ、自然に仏界に至ることができる。諸天の加護がないからといって、疑ってはいけない。現世が安穏でないことを嘆いてはいけない。私の弟子に朝夕、このことを教えてきたけれども、疑いを起こして皆、信心を捨ててしまったようである。拙い者の習性として、約束したことを、いざという時には忘れてしまうものである。
限界ギリギリ……。今こそ「まことの時」
ここまで読んでくださった創価学会員の方々の中には、「え! 知らなかったの?」と驚かれているかもしれません。
この一節は、とても有名で、私も学生の頃から何度も学んできました。どんな大変なことがあっても、信仰を疑ってはいけないんだ、と心に刻んでいたつもりでした。
でも、実際は、そうではなかったんです。まさにこの一節の通り、本当に苦しい時に今まで学んだことをすっかり忘れてしまい、「信仰に意味はあるのだろうか」と不信感を抱いてしまったのです。
そんな時、母からこの一節を通して、「あなたにとって、今が『まことの時』なのだから、絶対に負けちゃだめだよ」と励まされました。ハッと我に返り、「この苦しい状況を信心で乗り越えよう」と心を固めることができたのです。
苦しい状況はその後も続いていたものの、「今が『まことの時』」との言葉を胸に夫婦で励まし合い、ありがたくも母子共に健康な状態で、長女が生まれてきてくれました。
励まされる人から励ます人に
この経験を通して、750年以上も前に日蓮大聖人が記した励ましの言葉が、21世紀を生きる私の心に響いたことに感慨を覚えていました。しかし、改まって考えてみると、日蓮大聖人の言葉の力はもちろんですが、信頼する母がこの一節を紹介し、エールを送ってくれたことこそが、私の心を大きく揺り動かしたのだと分かります。
池田先生は御書を通じて、こう語られています。
「『法自ら弘まらず人・法を弘むる故に人法ともに尊し』(全856・新2200)――法は、ひとりでに弘まるのではない。人が法を弘めるのであり、だからこそ弘める人も弘まる法も、ともに尊い――と」(『池田大作全集』第88巻)
私に信仰者としての心構えを教えてくれた、その母に、昨年末、大きな病気が見つかりました。〝今度は私が励ます番!〟と意気込んで、いろいろ言葉をかけたり、入院手続きに付き添ったりと、あれこれ世話を焼こうとしたのですが、母の信仰心は鉄壁。なかなか手応えがありません。
病気になったと電話で明かされた時は、こんな様子でした。
私「症状はどうなの? 病気の進行具合とか……」
母「症状? 全然ないよ。それより、手術で入院するから聖教新聞をスマホで見られるようにしてほしいんだけど!」
病院での入院手続き中は、
私「何時から手術か、分かったら教えてね。題目送ります」
母「あら、ありがとう。あ、そうだ、悪いんだけどスマホをWi―Fiつないでくれる?」
もう、完全にスマホ相談員です。
ただ、妻いわく「お母さん、あなたが電話した時は、声のトーンがうれしそうだったよ」とのこと。少しは親孝行できたのかなと思っています。
新たな船出にどんな言葉を
さて、冒頭で聖教新聞のCMを褒めてくれた友人ですが、話を進める内に、お付き合いしている女性と近いうちに結婚するとの報告が。〝こいつにも大切な人ができたことで、「言葉と、生きていく」というフレーズが刺さったのかなぁ〟と、点と点がつながった気がしました。
結婚式も行う予定らしく、光栄なことに、私に友人代表あいさつをしてほしいとの依頼がありました。私なりの「言葉と、生きていく」経験を踏まえて、友人の新たな船出に、どんな言葉を贈ろうか、今からワクワクしながら考えています。