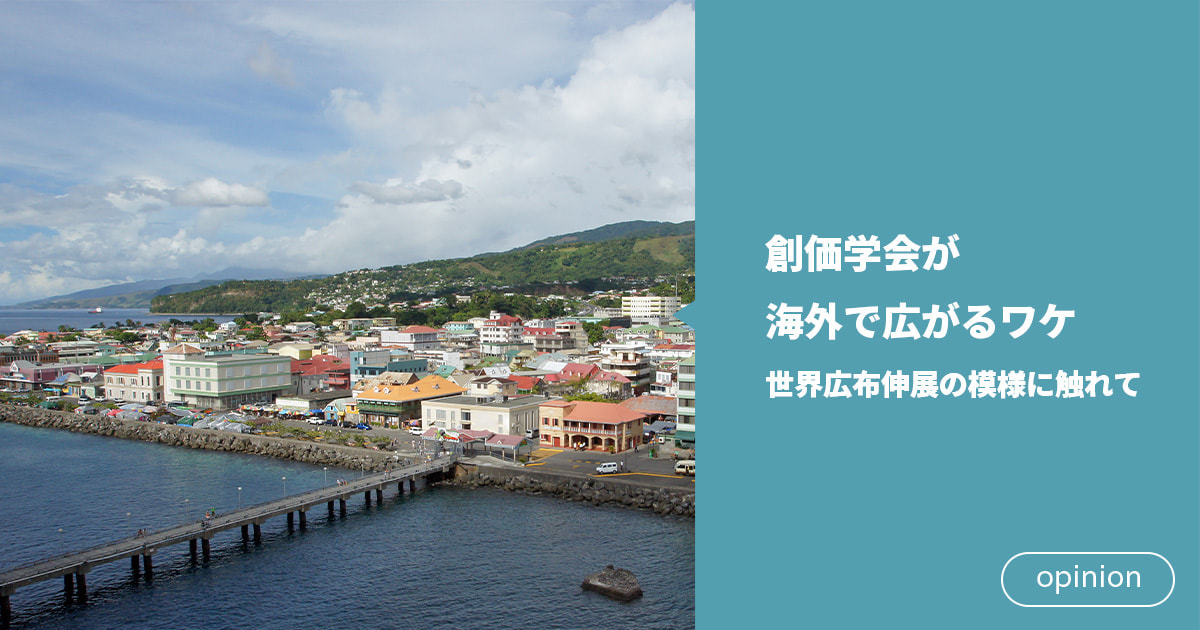クリスチャンの友人と語り合って気付いたこと

留学先のルームメイト
かれこれ10年前、アメリカ留学をしていた私は、「進化論」についてどう語るか悩んでいた。まさか、「進化論」が本当かどうかを語り合う日が来るとは思ってもみなかった。
当時、LA郊外の大学寮に住んでおり、キッチンと小さなテーブル、ベッドと机2つずつのこじんまりしたワンルームで、ルームメイトと宗教対話で盛り上がっていた。
彼女は敬虔なクリスチャンで、私が不躾にも「進化論ってどう考えてる?」って聞いてしまったがために、生命の起源など、多岐にわたる長い議論になってしまった。
日本の学校教育では、「進化論」をベースにしているし、私は、NHK「地球大進化」をこよなく愛していた。今まで学んできたことをつぎ込み、つたない英語で自分の考えを伝えた。
対して、彼女は、「神が世界を創造した」という「創造論」を大事にしていた。
キリスト教でも人によるが、「進化論」は宗教観と相違する部分があるため、実はとてもセンシティブな話題だった。今となっては、あまり深く考えずに「進化論」を話題にしてしまったことは、相手の信仰への理解が少なかったと反省している。
そのテーマについて、話せば話すほど、お互いの考え方の違いが鮮明になった。
しかし、彼女と話が合う話題があった。それは「生き方」について。
私は、リアルに“平和”を実現したいと思って、国際性を身に付けるため、留学をした。
彼女も、恵まれない子どもたちを幸せにしたいと、教育の道を学び深めるために、単身、海外に飛び込んだ。
お互いの考え方の根本には、宗教を信仰する中で学んだ「自他ともに幸福を目指す生き方」があった。教義や思想は違っても、目指す世界や生き方は一緒だった。
共通点が見つかり、「お互いに頑張ろう!」と決意しあうことができた。
ちなみに、彼女には、出会った初日に、
「自分は創価学会という仏教団体に入っていて、朝晩、勤行唱題で自分自身の中にある無限の可能性(仏性)を引き出していく実践をしているんだけど、やっても大丈夫かな?もちろん迷惑にならないボリュームで」と聞いたら、そこから宗教談義になり、一気に心の距離が縮まった。
なお、勤行唱題とは、仏壇の前に座って手を合わせ、経を読み、「南無妙法蓮華経」と唱えること。彼女は大歓迎で、私のお題目の音律を楽しんで聞いてくれたので、とてもありがたいルームメイトだった。
彼女はいつも「隣人愛」の精神で、私の健康や日々の生活を気にかけてくれ、姉妹のように仲良くしてくれた。彼女の姿の中に、信仰者としての生き方を学んだ。
帰国直前、彼女が私のために神への祈りを捧げてくれ、聖書をプレゼントしてくれたことは、良い思い出だ。「自分のために祈ってくれている」――その真心が本当に嬉しかった。私も彼女の幸せを祈ろうと決意した。
これが初めての友人との宗教をこえた交流だった。

温かいつながり
帰国後に出会ったある友人もキリスト教を信じていた。
その子とは、ごはんに行っては、お互いの近況や悩みを話し、宗教や哲学についても語り合う。創価学会の座談会に参加してくれたこともあった。
友人には、「どうしてこの子がこんなに苦しい思いをしなくちゃいけないんだろう」と勝手にこちらが思うくらい、いろんな人生の苦労があった。そんな中でも、希望を忘れずに、いろんなことを学び続ける姿勢にいつも触発をもらっている。
私も私なりに、心の葛藤や家族の病気など、いろんな経験をしてきた。日々の信仰の実践の中で、自分の悩みを一つ一つ乗り越えていること、悩みがあるからこそ誰かを励ませる自分になれたことなどを、率直に語ってきた。

池田先生は「『真の対話』は、相手を尊敬し、相手から学ぶことだ。そこに互いの向上があり、喜びがある」と語られている。
私はキリスト教について、ルームメイトにもらった聖書を読んでみたり、疑問に思ったことを友人から教えてもらったりして、自分なりに学びはじめている。
まだ勉強途中なので、間違っていたら申し訳ないが、その友人とは「宿命」に対する考え方が異なるように思う。
だからなのか、ある時、こんなことを言ってくれた。
「いろんな悩みがあっても、「すべてを価値あるものにできる」と確信して、希望を持って生きているよね。創価の『価値を創造する』『宿命を使命に変える』っていう考えを実際にやってて、本当にすごいなっておもう。それに、いつもまっすぐ信念に生きてて、触発される。自分も頑張る」と。
また、私の近所には、キリスト教ではないが、他宗教の教会があり、その信仰を持つ御一家とは、祖母の代から三世代にわたり交流を深めてきた。お互いに、家族の病などで大変な時には励ましを送りあい、温かなつながりを築いてきた。
宗教を超えた対話の大切さ
次元は異なるが、池田先生は、イスラム教のマジッド・テヘラニアン博士、ヒンズー教のベッド・ナンダ博士に代表されるように、様々な宗教や背景に持つ方々と対話し、世界中に友情の道を開かれた。
ベッド・ナンダ博士との対談の中で、対話の重要性について、池田先生は下記のように言及されている。
「世界を回り、さまざまな文化的、宗教的、思想的背景のリーダーや識者と対話してきましたが、実感したのは、異なる文明の中で生まれ、違った文化的背景のなかで育ってきたとしても、「相互理解は可能である」ということです。
すべての人間には本来、等しく豊かな「善性」が備わっています。
その「善性」に呼びかけ、呼び覚ましていく「対話」を基軸にすれば、理解し合える。友情も結べるのです。」(『インドの精神』(東洋哲学研究所))

昨年は、原田会長がフランシスコ教皇と会見し、今年に入ってからは、谷川SGI理事長がスペイン仏教連盟会長とも懇談している。
核廃絶の取り組み等では、「信仰を基盤とした団体」(FBO)として様々な宗教と協力しながら、草の根の平和運動を進めている。
個人的な考えだが、信仰や哲学を基盤とした活動は、コアがぶれないし、だからこそ、難しい状況でも希望を持って、進むことができるのではと感じる。
地球的課題が山積する現代だからこそ私たちが、自他共の幸福のため、社会・世界のために連帯を広げていくことが大切だと感じる。
友人との語り合いを通して
私は友人とあれこれ話すことが楽しい。それは、考え方も育ってきたバックグラウンドも違うからこそ、話すことでたくさんの発見があるからだ。
新しい思想や価値観に出会えるし、その子がたとえ違う宗教を信仰していたとしても、共感しあえる部分を大切にしながら、共に学びあい、高めあっていけると実感する。
そして、それは、自分の心が大きく広がる経験でもあり、出会いの一つ一つが人生を豊かに彩ってくれる。
これからも、自分の身近な場所から、どんな違いにもとらわれずに、心の絆を結ぶ友情の対話に挑戦していきたい。