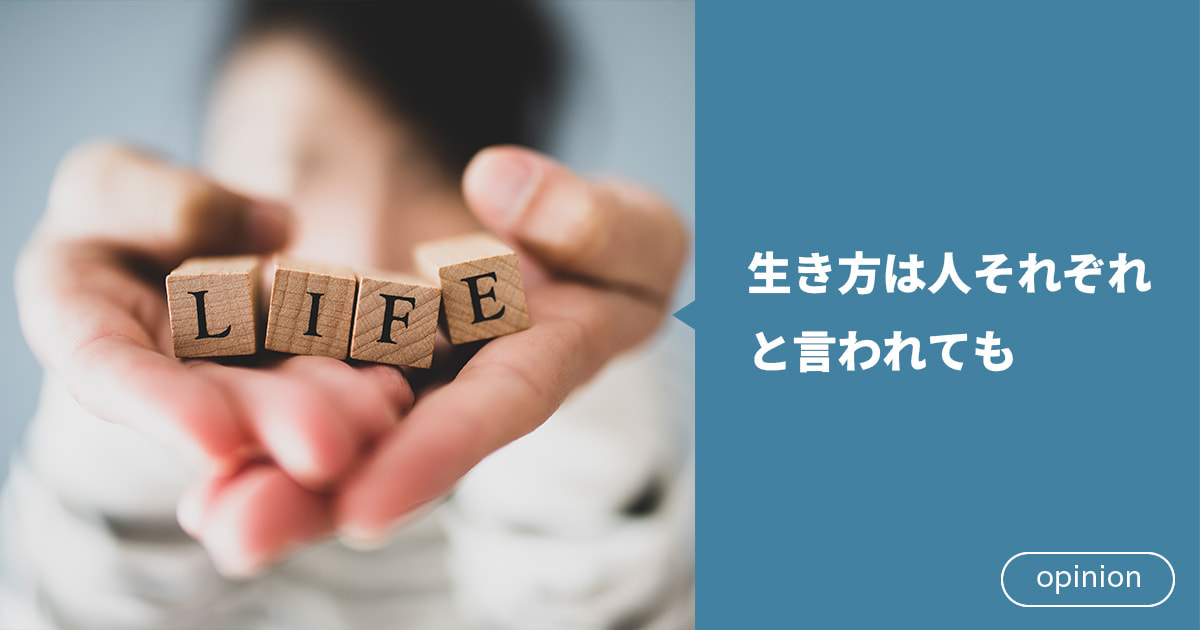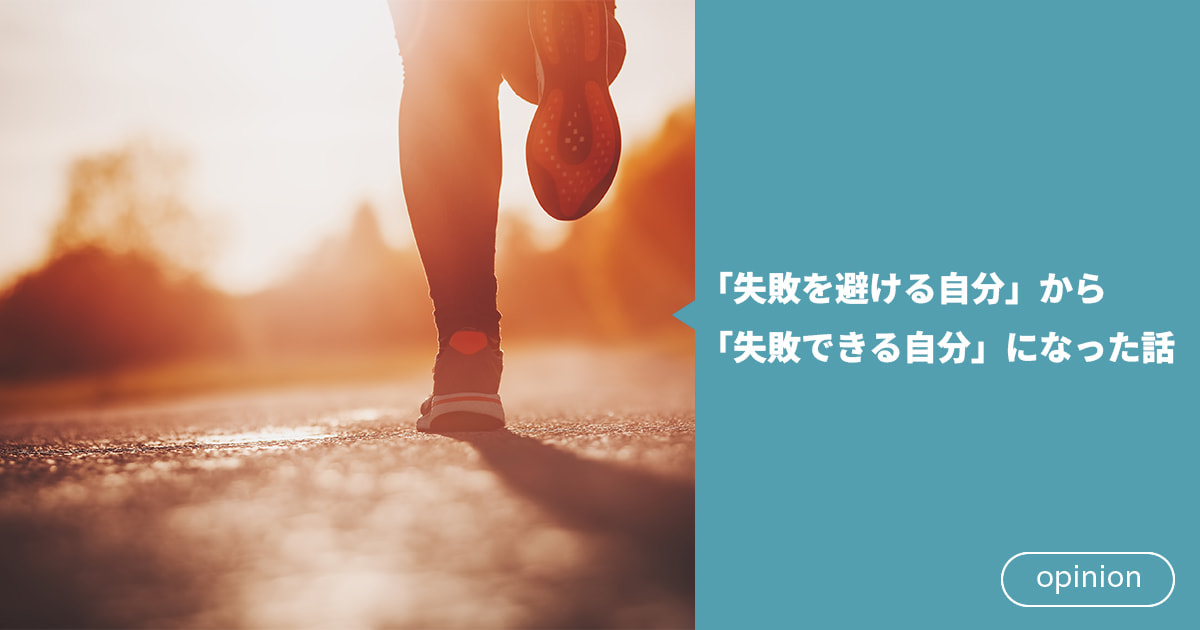「ヒョウのおなか」って、何色だと思いますか。
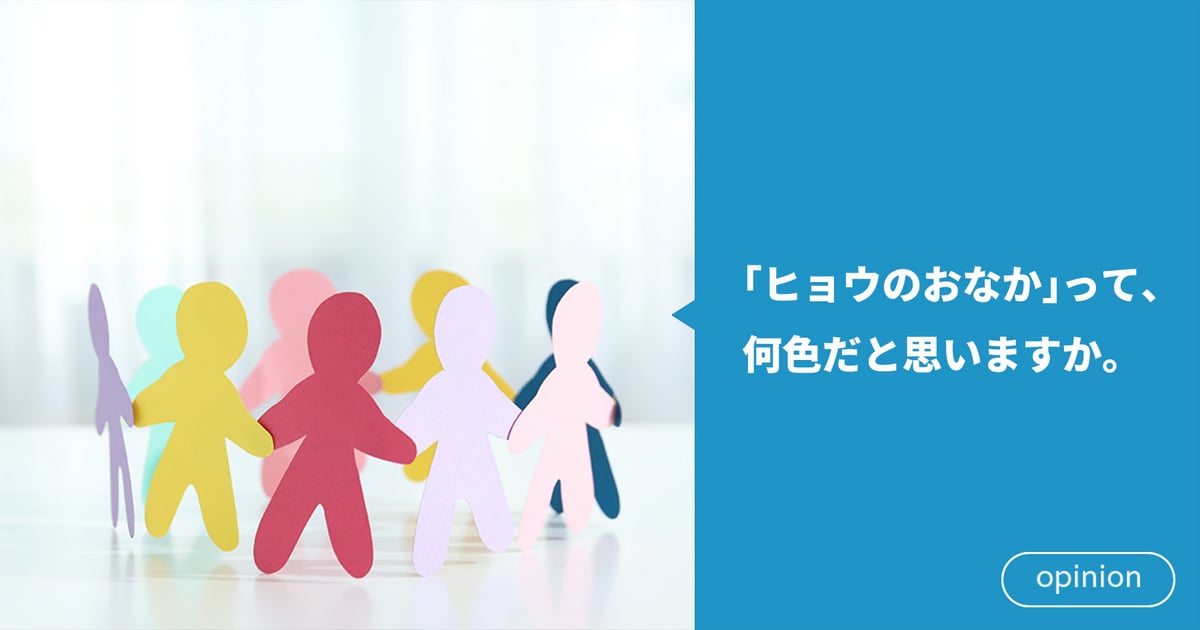
突然ですが、問題です。「ヒョウのおなか」って、何色か知っていますか。
正解は――「白」だそうです(改訂新版『世界大百科事典』より)。
黄色や黒のイメージが強いから、あまり知られていないですよね。
「一斑を見て全豹を卜す」という言葉があります。
ヒョウの毛皮の一部しか見ていないのに、「ヒョウの全身は黄色と黒なんだ!」と思い込んでしまうことを言います。そうです。お腹は「白」なのに、です。そこに気づいていない。もしかしたら、「見ようともしていない」のかもしれません。
この言葉は、物事の「一部分」だけを見て、「全体」を推し量っちゃ「ダメだよ」と教えてくれています。
「そりゃそうだ」「当たり前じゃん」と思うかもしれません。
でも、よく考えてみてください。私たち人間は「ヒョウ」に対してだけじゃなく、知らず知らずのうちに「人」に対しても「一部分」しか見ていなかったな……なんてことはありませんか。
表面的な性格や外見――たとえば「彼は明るい」「あの子は暗い」「彼女は派手」「あの人は地味」とか――だけに捉われて、その人の全てを分かったような気でいた、なんてことはありませんか。
ひどい場合になると、「噂話」や「評価」など一部の人の言葉を信じて、「あの人は素晴らしい」「彼はダメ」と判断してしまった、なんてことも……。
「ギクッ」とした人もいるはずです。でも安心してください。
じつはこれ、誰もが陥りがちなことなんです。
「一面だけ」は、ダメなこと?
というのも、人間は無意識のうちに、分類や区別をしたがってしまう生き物なのだそうです。
(SEKAI NO OWARIの「Habit」にも、似たような歌詞がありましたね)
京都大学の竹沢泰子名誉教授は、「分類するのは人間の普遍的な本質」と言います。
「人は、目や耳、本などから得たさまざまな情報を、脳の中に箱のようなものをたくさん作ってそこに投げ込んでいます。何か刺激を受けたら、箱に入っていた情報を呼び起こし、新しく入ってきたものと比較するなどを行って理解したり予測したりする。一つひとつの箱の中にはまたいくつかの箱があり、その中にさらに箱がありと、こういうふうにして情報を分類して整理しないと、新しいものを理解できないのです」
(「ほとんど0円大学」HPインタビュー記事より引用)
そして、
「問題なのは、物と同じように人もカテゴリーを作って分けてしまうことです」
(「ほとんど0円大学」HPインタビュー記事より引用)
と語っています。
さらに、人は「分類できない境界上のものに不安を抱きがち」なことも分かっているそうです。
だからこそ、人の「一面」「一部分」「表面」だけであったとしても、とにかく「早く分類してしまおう!」と思ってしまうのかもしれません。
そうなんです。だから、「ヒョウの全身は黄色と黒!」と考えてしまうのも、誰もが陥りがちなことなんですね。
次々に飛び込んでくる情報を、脳の中で手際よく処理して「箱」に入れるために、「仕方なく」一面だけを見て相手を判断している、とも言えるかもしれません。
ここで、2つの心理傾向を紹介します。
第一に「ステレオタイプ」。
例えば、国籍や出身地などを聞いた瞬間、思い込みやイメージでその人を判断してしまったことはありませんか。「彼は、〇〇人だから」「彼女は、〇〇出身だから」というような会話を耳にしたこともあると思います。
また、「あの人はあの宗教を信じているから」と宗教への漠然としたイメージを、その人のイメージに置き換えてしまっている、なんていうケースも見られます。あとは、「あの人はA型だから、〇〇だよね」とか。血液型だけで、その人を推し量っちゃう、なんてこともあるかもしれません。
第二に「確証バイアス」です。「バイアス」とは、先入観や偏見を意味します。
確証バイアスとは、自分の思い込みや願望を裏付けるような「情報」ばかりに目が向いてしまうことです。
「こうだ!」と信じたことを疑えない。自分の考えや思い込みと一致しない時は「例外」と決めつけてしまう。「きっと事実はこうだろう」と都合の良いように解釈し、「自分は正しい!」と盲信してしまうことを言います。
この2つの心理傾向のように、私たちが日頃、無意識に思い込んでしまっている偏見のことを「アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)」と言うそうです。「無意識の偏見」と言われると、ちょっと怖いですね……。
これを知って、ふと脳裏をよぎったことがありました――。
それは、今から約750年前の史実。鎌倉時代の武士・四条金吾のことです。
「そんな昔のこと」と思った皆さんも、もう少しだけ、お付き合いいただけたら有難いです。
武芸と医術に秀でた金吾は、主君の江間氏から大切にされていました。ですが、金吾が江間氏に法華経を勧めたことで、事態は一変。念仏を信じていた江間氏は激怒し、金吾を遠ざけます。
金吾の活躍に嫉妬していた同僚たちは「今がチャンス!」とばかりに、金吾に関する誹謗中傷を江間氏の耳に吹き込みます。
この時、主君は“念仏を信じる私に、法華経を勧めてきた金吾のことだ。きっと悪いことをしているに違いない”と、同僚の讒言をうのみにしてしまったのではないでしょうか。
そうなんです。この時、主君の心の中にも「アンコンシャス・バイアス」が潜んでいたかもしれないんです。
結局、誠実を貫いた金吾の振る舞いによって、江間氏の信頼を取り戻し、同僚たちの悪事は明らかになりました。ですが、そもそも江間氏が「無意識の偏見」に翻弄されなければ、金吾が苦しむことはありませんでした。
これは、750年前の昔話ではないのです。実は今の日本社会でも、同じようなことが起きています。
「アンコンシャス・バイアス」への対応から目を背けることは、組織にとって大きなマイナスです。
特に、リーダーにとっては、メンバーの功績を正しく評価し、良好な人間関係を保つ上でも、「アンコンシャス・バイアス」について知識を得、自身の振る舞いに生かしていくことが欠かせなくなっています。
本年2月6日、鳥取県は「アンコンシャス・バイアス」を解消するための新たな組織を設置することを発表しました(共同通信)が、近年、日本でも対応に動き出す企業や団体が増えています。
ポジティブなバイアス(偏見)
今まで書いてきたことは、「私とは関係ない誰か」の話ではありません。
「アンコンシャス・バイアス」は、誰もがもっているものです。
生まれ持った人間としての習性を直すことは簡単ではありません。
でも、いえ、だからこそ、コミュニケーションを取る時、相手を「多面的」に知ろうとする努力が必要なのかもしれません。
「表面的」なものや「一部分」だけを見て、相手を分類しようとする自分自身に「STOP」をかけ、相手の本質に迫ろうと、多角的に質問したり、心ゆくまでじっくり話してみたり。そんな時間が増えれば増えるほど、「無意識の偏見」は減り、「この人は僕のことを分かってくれている(分かろうとしてくれている)」という「本当の信頼」が生まれていくのではないでしょうか。
きっと、創価学会が世界的に発展をしてきた要因の一つにも、「表面的な」を超えた「多面的な」コミュニケーションが広がっていったからだと感じています。
人づての話だけで判断しない。自分の眼で相手を見る。自分の耳で声を聞く。「あなたのことが知りたい」と対話を重ねるからこそ、「多面的な」相手の実像が見えてくるのだと思います。
忘れられない言葉があります――。
オーストリアに行った際、新入会の青年が語っていました。「創価学会に入会して、一番良かったのは、目には見えない他者の苦悩や心を『知りたい』と思える自分になれたことです。『寄り添う』とは『相手を知ろうと努力を続けること』だと教わりました」と。
なぜ、相手を知りたいと思えるのか。その背景にあるのは「全ての人に仏性がある」「誰もが、必ず、今世で絶対的な幸せを実感することができる」という、ポジティブなバイアス(偏見)です。
バイアスも悪いものばかりではないんですね。
きっと、この「ポジティブなバイアス」が、瞬時に人を「分類」しようとする「無意識の偏見」に打ち勝つキーワードなのかもしれません。
「知っているつもり」にならず、「相手を知ろう」と努力を続ける――それこそが、相手への尊敬の証であり、私たち学会員が目指す「人の振る舞い」なのだと思うのです。