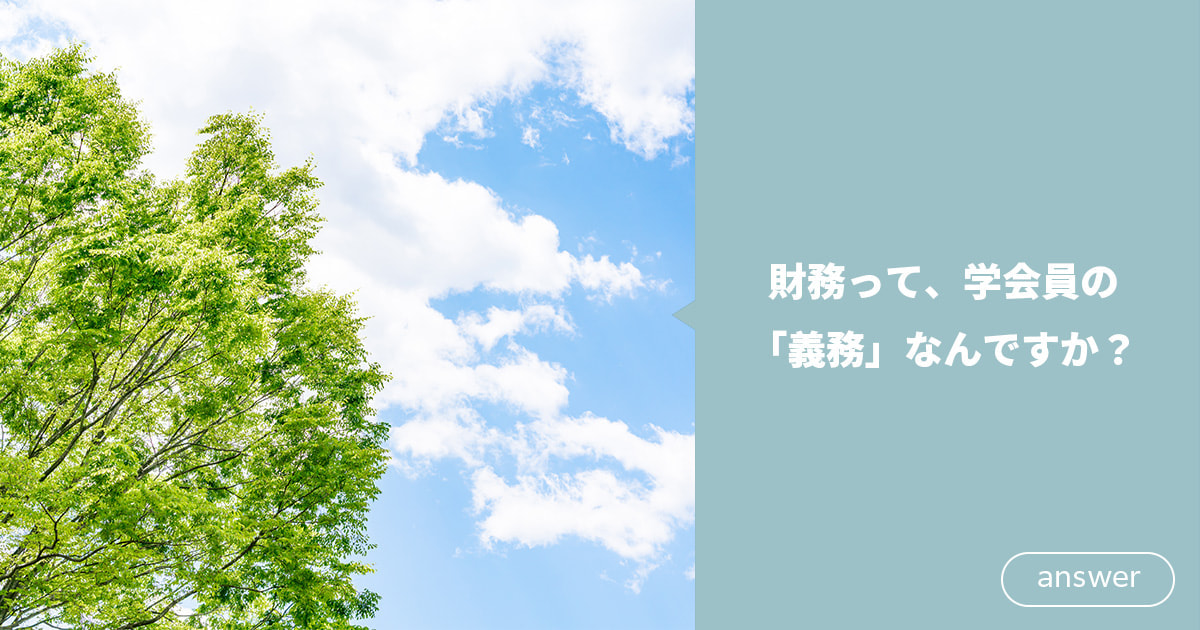私にとっての「財務」ってなんだろう?

「お前のところの宗教ってさ、どれくらいお金取られるの?」――ある日、友達からそんな質問をされた。
まず、創価学会に「会員費」はない。所属しているから払うお金は1円もない。聖教新聞を購読するための購読料や、会合に参加するための交通費も、強制ではなく納得の上で受け入れている。友達は「お布施」を強制されているんじゃないかと思ったのかもしれない。
創価学会の「財務」とは?
創価学会では毎年、年末になると実施される「財務」という取り組みがある。これも強制ではなく個人に委ねられていて、私は友人に、この財務に取り組んだ話をした。でも彼は腑に落ちない様子。確かに、宗教団体に寄付する人の気持ちって、イメージしづらいだろうな……。
なので、自分にとって、学会の財務とは何かを改めて考えてみた。
わが家は両親の代から創価学会の信仰を続けてきた。子どもの頃の私は知らなかったが、仕事で難局を迎えたときや私が不登校になったとき、両親は祈り、学会活動に取り組んだ。結果的に不況のときも生活に困らず、私も進学して無事に社会人となった。私自身も、引きこもりの状態を変えたいと思い、自主的に祈るようになった。そのおかげで、自分の中に生き方の軸ができたと思っている。
創価学会員が実践する仏法は、「誰もが必ず幸福になれる」と説かれていて、個人の幸せだけではなくて、縁する人も幸せにしていこうという目的観がある。私自身もこの信仰で生き方の軸を学び、学会組織の中でたくさんの励ましと触発を与えてもらい、思ってもみなかった充実の人生を生きている。その感謝の意味も込めて、創価学会の取り組みを応援したいと思い、少しでもサポートになればと毎年、心ばかりの財務をしている。
人間の幸福を目指す活動が、もっと盛り上がってほしい
全然分野は違うけど、今の世の中、「推し活」にお金を使っている人はたくさんいる。グッズを買ったり、ライブに行ったりするだけでなく、好きな人や団体に直接寄付することもできる。また、インターネットを通じて寄付を募るクラウドファンディングも広く認知されてきた。
こうしたお金の使い方には、好きな人の役に立ってほしいとか、世の中のためになってほしいという寄付者の思いがある。もちろん、生活に支障をきたすほどお金をかけるのは慎むべきだし、周りも止めた方がいい。
私にとっての「財務」は、推し活に近い感覚だ。もちろん趣味と信仰は同列ではないけれど、「人間の幸福を目指す活動が、もっと盛り上がってほしい」という気持ちの表明として寄付する。だから、「お金を取られている」という感覚はない。
財務の時期になると、仏法の「供養の精神」を勉強する機会がある。私の胸に響いたのは、日蓮大聖人が、ご自身を支えるために白米などを届けた門下に対し、返事をしたためた手紙の一節だ。
凡夫は志と申す文字を心えて仏になり候なり。
(白米一俵御書、新2053・全1596)
現代語に訳すと、「人々は『志』という文字を心得て仏になる」という意味になる。死者への供え物や冥福を祈る行為を示す「供養」という言葉には、もともと「尊敬の気持ちで種々の行いをすること」という意味があるらしい。その点からも、供養にとって大切なのは「自分の差し出すものが役に立ってほしい」という思いだ。
財務について、週刊誌などでは「巨大な宗教団体が信者からお金を巻き上げている」ような言説が多いが、そんなことはないと断言できる。なぜなら財務は、周りの人間が「強制」することはできないからだ。なぜなら、財務は誰でもできるわけではなく、条件を満たした会員である必要がある。さらに、本人が財務の意思を示す「広布部員」の申し込みが必要だ。
冒頭の話に戻るけれど、わが家が経済的な苦境に陥ったときも、両親は財務に挑戦してきた。その後、不思議とお金に困らない生活ができたことを「財務の功徳だ」と感謝していた。きっとそうなのだろう。言うに尽くせぬ苦境にあっても信心という松明(たいまつ)を離さず、学会への感謝を忘れずに生き抜く。その姿に信仰への純粋な志と、「信じ抜く人の強さ」を教えられた。真心と感謝に生きる両親の生き方を、誇らしく思う。