“言葉の力”を自覚せよ――事実無根の報道に思う
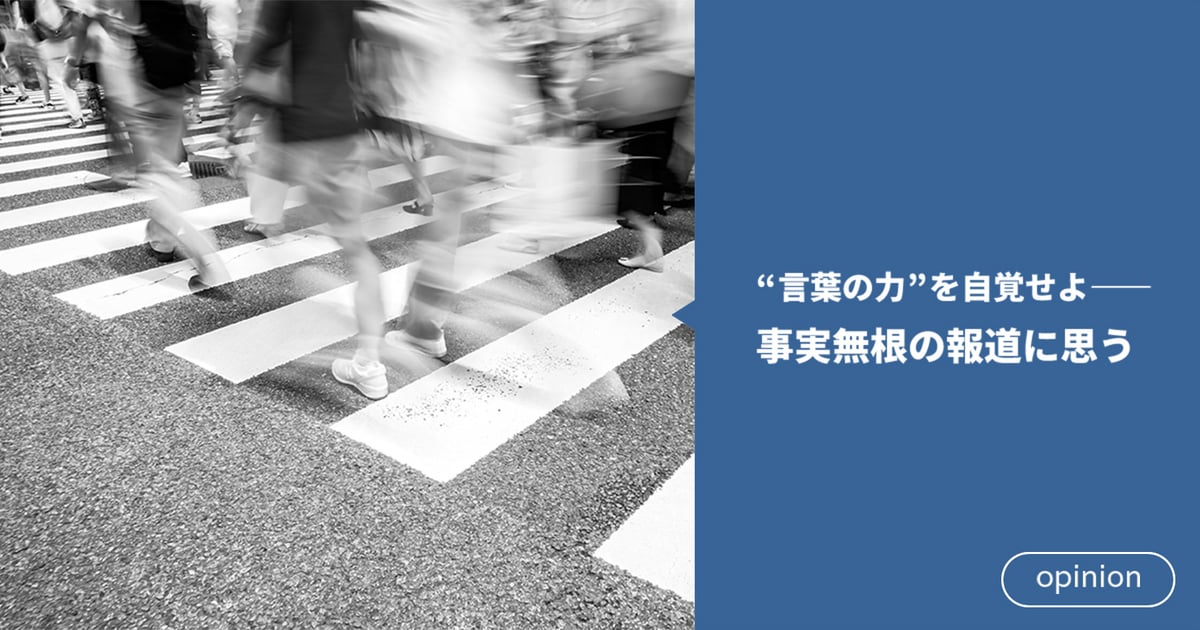
言葉のもつ力は大きい。他者を励ます薬にもなれば、命さえ奪う凶器にも成り果てる。情報を発信する者は誰であれ、言葉のもつ影響力の大きさを絶対に忘れてはならない。
情報発信の大前提は、いうまでもなく「事実」であることだ。憶測や根拠のない主張をすれば、その情報を受けた人たちを混乱に陥れ、扱われた個人や団体の名誉にも関わる。
今やあらゆる発信が、SNSで誹謗中傷に使われてしまう。虚偽の発信は、虚偽というだけで厄介だが、拡散によって誹謗中傷を誘発する点でも深刻だ。誰もが発信者になれる時代。あらゆる情報が即座に得られる一方、真偽不明な情報や明確な誤りが、さも正しいかのように拡散されてしまうことがある。SNSでの誹謗中傷は、エスカレートするとおびただしい量の非難が寄せられ、命が失われる痛ましい出来事も起きている。
こうした被害を防ぐべく、日本では2022年7月、改正刑法の一部が施行。「事実を摘示せずに、不特定又は多数の人が認識できる状態で、他人に対する軽蔑の表示を行う」(法務省)ことが要件の「侮辱罪」の厳罰化がなされ、懲役が刑の上限になった。さらに同年10月には改正プロバイダ責任制限法が施行。問題のある投稿をした者の情報開示を速やかに行えるようになった。しかしそれでも、SNS上での誹謗中傷は止むことがない。
事実無根の「連休中日要望」報道
最近も、メディアの質が問われた事象が発生した。1月14日、日本経済新聞はインターネット上に「参院選7月20日軸、異例の三連休中日に 公明党が要望」と題する記事を発表。公明党が三連休の中日を投開票日にするよう要望したかのような見出しだ。記事では参院選の投開票日について「東京都議選との接近を避けるよう求めた公明党」「24年12月の自公党首会談で公明党の斉藤鉄夫代表が日程が近接しないよう首相に要請した」とあり、公明党の要望とは「都議選と参院選の投開票日を遠ざけること」であることは明白だ。見出しから類推される「三連休中日の実施」を要望したわけではなく、ここに事実を誤認させるミスリードが生まれている。さらに「遠出する人が増える連休中日を投開票日とすれば、野党に向かいやすい浮動票が減り与党に有利に働くとの見方がある」と続く。
この記事がX(旧ツイッター)で瞬く間に拡散され、政治家やインフルエンサーがこの記事を引用し、公明を厳しい言葉で糾弾した。元安芸高田市長の石丸伸二氏も「恥ずかしくないのか公明党は。与党の立場を使って党利党略に勤しむなど許されると思うな」と言及。有象無象の公明批判が吹き荒れた。
翌15日午前には産経新聞が、先の報道によるSNSの紛糾をまとめた記事「公明党『要望』報道がXで物議『投票率下げる思惑か』 参院選は連休中日7月20日軸に」を発表。公明党の要望と党利をほのめかす見出しがつけられ、「組織票を期待できる公明側に有利に運ぶとの思惑が指摘されている」などと報道された。
公明党は15日午後、“参院選の選挙日を三連休の中日に要望した事実はない”と斉藤代表が語る動画を発表。代表は、投票率が下がれば公明党の得票も下がる近年の事実を説明し、「公明党が投票率が下がれば有利になるということは全くありませんので、そのような要望を出す理由もない」と訴えた。この動画が拡散され、16日にはNHKニュースや読売新聞に「公明が投票日を要望」の事実はないとする斉藤代表の発言が取り上げられた。批判を削除し、訂正・謝罪をする者もあったが、誤った見解を拡散したことに言及や訂正がない者も少なくない。先の石丸氏もその一人である。
ミスリードを誘う見出しは、これまでも週刊誌等で使われてきた。見出しだけを見る人も多いことから、影響力は決して低くはない。SNSでは表示回数が多いほど収益を得られるシステムから、事実関係を無視した極端な見出し・内容によってインプレッション(表示回数)を稼ぐ者がいる。これが偽・誤情報の拡散を助長しているとの指摘もある。先の記事がミスリードを誘う見出しだったことに対してXでは“新聞社がインプ稼ぎをするのか”とのコメントもあった。「社会の木鐸」であるはずの新聞が、存在しない事実があったかのような印象を広めることは、信頼を自ら地に落とす行為である。
止まぬ誹謗、残る中傷
この報道がSNSを賑わせた後の18日夜、兵庫県の元県議(50)が亡くなるというニュースが報じられた。元県議は県知事の文書告発問題の究明に取り組む中、インターネットでの誹謗中傷にさらされ、「一身上の都合」で24年11月に議員を辞職。自死とみられ、誹謗中傷が原因ではないかといわれている。亡くなった後も、本人へのSNS上での誹謗中傷は止むことがない。
19日、政治団体の党首である立花孝志氏はXで、元県議は「昨年9月ごろから兵庫県警からの継続的な任意の取り調べを受けていました」と投稿し、自身の動画チャンネルでも「元県会議員、どうも明日逮捕される予定だったそうです」と発言していたという(朝日新聞デジタル)。
20日午前、兵庫県警の村井紀之本部長は「個別案件の捜査で言及することは差し控えているが、事案の特殊性に鑑みて答弁する」と異例であることを前置きした上で、元県議について「任意の取り調べをしたことはなく、ましてや逮捕するという話は全くない」「全くの事実無根で、明白な虚偽がSNSで拡散されていることについては極めて遺憾」(時事通信ニュース)と述べ、立花氏の投稿内容を完全に否定した。その後、立花氏は自身の発言を事実ではなかったとして謝罪。しかし、この発言の影響で元県議に投げつけられた言葉は残り続ける。亡くなった直後の人物に対して軽々に発言をすることも無神経の極みだが、故人の名誉に関わる「事実に基づかない憶測」を拡散し、死屍に鞭打つ行為は断じて許されるものではない。
「真実のみを書く」信念
情報を受け取る側は、正しさを見極める目を養いたい。インフルエンサーが誰かの批判をした際、その発信をうのみにして拡散してしまえば、無自覚に「傷害」「名誉毀損」に加担し、その誰かの生活を壊してしまうかもしれない。何によって正しいと裏付けられるのか、一次情報を確認したい。複数の報道を読み比べたり、反対の意見に触れることも大切だ。善意ですぐに伝えようとして誤情報が広がるケースもある。自分が発信する際は、その情報が正しいと説明できるか検討し、言葉がもたらす影響に責任をもつ覚悟が必要だ。
「言論の自由」「表現の自由」があるのだから、どんな言論も許されるべきだという主張がある。しかし、人間としての尊厳、生命の価値すらも軽んじてよいとする論調は、断じて容認することはできない。事実に基づかない話であればなおさらだ。
ノーベル文学賞作家のショーロホフは「すべての作りもので不自然なもの、すべての虚偽のものは、時間の経過とともに消えさり、長くは生きられないでしょう」とつづった。嫉妬によって「盗作である」等の非難を受け続けた彼は、「真実のみを書く」ことを執筆の信念とした。虚偽のものが真実にすり替わろうとする今、この言葉は輝きを放つ。情報が氾濫する世界に生きる一人の青年として、人を不幸に陥れる虚偽を打ち砕き、真実を追究して世に示すこと、そして言葉の力によって人々に希望を与えることが、メディアの使命でなければならないと固く信ずる。人間の連帯と幸福に寄与する言論の創出へ、さらに取り組む決意である。

