「聞く」ために「聞いてもらう」 多様な人が集まる創価の世界だからこそ感じたメリット
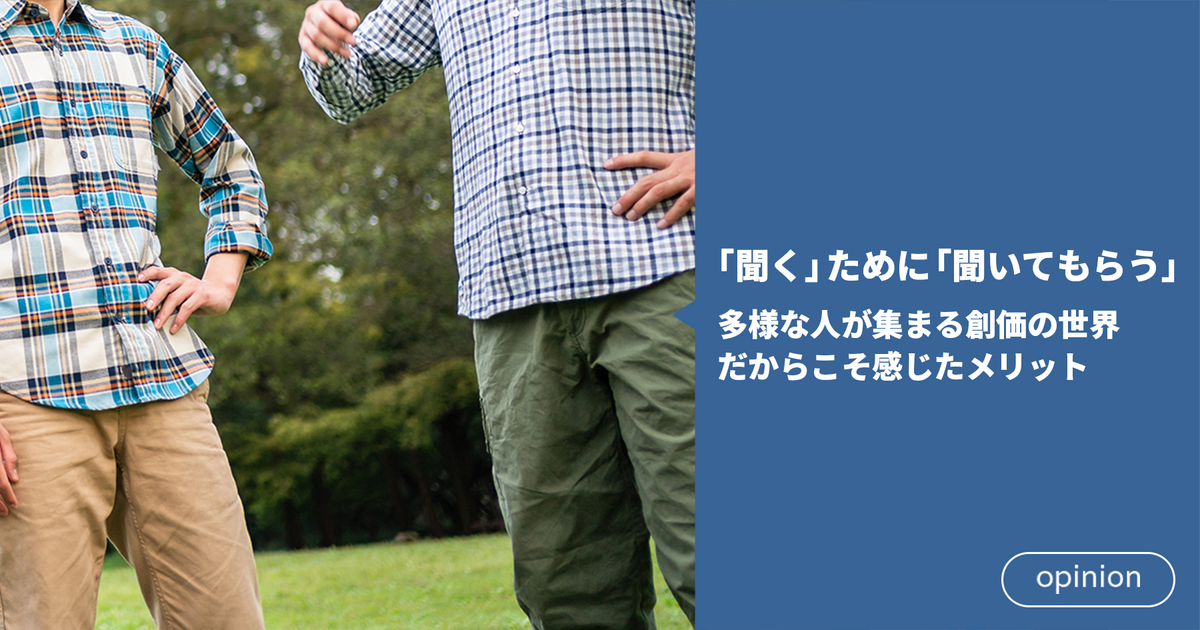
先輩と食事した時のこと。仕事の話題になり、「休みはあるんですか」と聞くと、相手からは「毎日仕事しているんだ」と。「めちゃくちゃ大変ですね!」。そんな私のリアクションに対して、その先輩からは、怪訝な顔をしながら「楽しいんで全然大丈夫です」と意外な答えが返ってきました。
世間一般からすれば、「毎日、仕事がある」のは大変です。というより、法令違反です(補足ですが、この人は個人事業主)。それでも中には、どんなに仕事が忙しくても大変に思わない人もいます。
何気ないやり取りではありますが、「仕事が忙しい=大変」と、自己の価値観に基づいて脊髄反射的に決めてしまったなと反省するとともに、相手の感覚や経験を想像・理解しながら人の話を聞くことの難しさを実感した一コマでした。
「聞く力」を磨くには
この出来事をきっかけに、「聞く力」を磨くにはどうしたらよいか考えるようになり、本屋である本を手に取りました。臨床心理学者・東畑開人氏の『聞く技術 聞いてもらう技術』です。
東畑氏は、人の話を「聞く」ことが不全に陥っていると指摘します。相手の話を言葉通りに受け取れない。相手の言うことが頭に入ってこない。東畑氏は、その理由を当人が相手から「話を聞いてもらえていない」と感じているからだと分析しています。
「あなたが話を聞けないのは、あなたの話を聞いてもらっていないからです。心が追い詰められ、脅かされている時には、僕らは人の話を聞けません」
(『聞く技術 聞いてもらう技術』ちくま新書)
「聞いてもらう」からこそ「聞く」ことができる。この感覚は、私の実感としても当てはまります。何かに行き詰まった時は、人の話が全く入ってこない。それが、誰かに話を聞いてもらうと、心が軽くなって、相手に心を向ける余裕も生まれます。聞いてもらえる人がいることは安心感につながります。
東畑氏は、「聞く」が不全に陥っている理由として、「孤立」の問題を挙げています。内閣府が令和5年に実施した「孤独・孤立の実態把握に関する全国調査」では、孤独感がある人は全体の約4割。直接会う・電話・SNS・メールといった手段で友人らとの連絡が少ないと、孤独感を感じる人も多いとの結果が出ました。話を聞いてもらう機会の減少が、聞くことを難しくしているのではないかと推察されます。
「聞く」「聞いてもらう」のサイクル
その中にあって、創価学会には、コミュニケーションの場があります。座談会と呼ばれる地域の集まりがあり、家庭訪問など、学会員との日頃の関わりの中には、相手の話を聞くことも、自分の話を聞いてもらうこともあります。話を聞いてもらった人が、今度は誰かの話を聞く側にーーこうした「聞く」「聞いてもらう」のサイクルが、創価学会の中には回っているのだと思います。
学会の集まりには、世代や人種、性別、仕事の壁を超えて参加しており、普段の人間関係では接することのできない、人生経験や夢を持った人がいることが魅力的だと思います。
仕事で結果を出すコツを聞きたい、同じ悩みを乗り越えた人に相談したい。こんな風に「この人の話を聞きたいな」「この人に話を聞いてほしいな」と思えることが多いです。その人にしか語れない珠玉の体験談を聞き、自身の話を聞いてもらいアドバイスをもらう中で、人生を前向きに進めていくことができます。
自分の半生を振り返ってみても、進路や仕事で壁にぶつかった時、創価学会の先輩に話を聞いてもらったことが転換点になりました。そうした先輩たちも、学会の中で話を聞いてもらい、人生を良い方向へ変えていったことが「聞く」につながっているのだと思います。
普段の暮らしの中で「聞く」を大切にし、誰かに聞いてもらえて「安心した」と思ってもらえるような、幅広い良好な人間関係をつくりながら、充実した人生を送っていきたいと思います。
