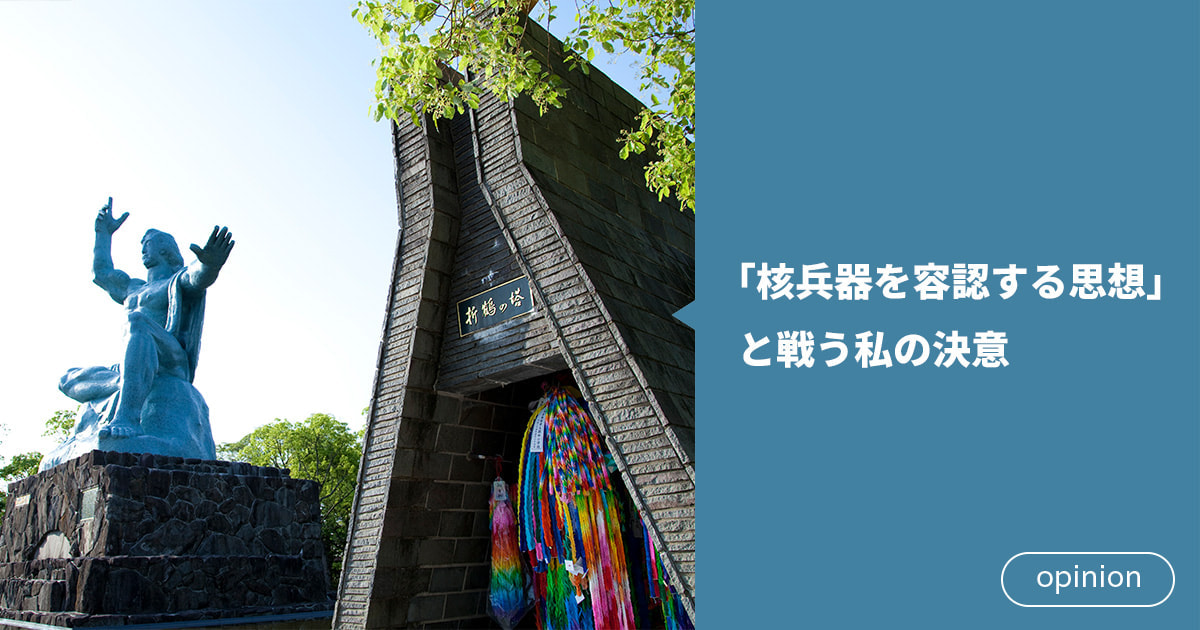核兵器禁止条約の発効に思う

「核兵器禁止条約」が、今月22日に発効する。この条約の歴史的意義は、1970年に発効した、NPT(核不拡散条約)との違いを浮き彫りにすると分かりやすい。
NPTとはその名の通り、核兵器を「拡散しない」ための条約。すでに核保有国だったアメリカ・ロシア・イギリス・フランス・中国の5カ国には、(事実上、保有を認めた上で)核軍縮の義務を課し、その他の国々には保有を禁じたものである。
一方の「禁止条約」は、核兵器の保有や使用等を、一切の例外なく禁じている。全世界に対して一律に、核兵器の存在そのものを否定した、初めての国際条約だ。
核兵器は“絶対悪”――学会の平和運動の原点である、戸田先生の「原水爆禁止宣言」(1957年9月8日)の精神が、まさに具現化された禁止条約であると思えてならない。
きょう15日付の聖教新聞には、国連軍縮担当上級代表を務めたセルジオ・ドゥアルテ氏のインタビューが掲載されている。禁止条約の誕生を後押ししたSGIの貢献を、氏は高く評価している。
条約には、核保有国や、核兵器の現実的な脅威にさらされる国々は加盟していない。日本も未加盟である。外交や安全保障の上での、さまざまな思惑が交錯していることは容易に想像がつく。
このことを巡り、一部のインターネットやSNS上では、日本政府に対する批判を目にする。その矛先は連立政権を組む公明党、そしてその支持母体である学会にも向いている。“公明党は、なぜ禁止条約を推進しないのか”“学会員は、公明党の姿勢をどう見るのか”等々。
こうした発言に、違和感を覚えるのは、私だけだろうか。
まず知るべきは、日本政府が「核兵器廃絶というゴールは共有している」とし、核保有国と非核保有国の「橋渡し役」を目指すと明言していること。“政府は核廃絶に反対”などというのは的外れな批判である。
そして公明党は、発行後1年以内に、そしてその後は2年に一度、開かれる禁止条約の締約国会議で、日本がオブザーバー(未批准国でも参加可)として参加するよう訴えている。禁止条約を実効性のあるものにするべく、具体的に汗をかいているのである。さらには、同会議の広島・長崎での開催を誘致すべきと、政府に申し入れもしている。公明党は、リアリズム(現実主義)である政治の世界で、核兵器廃絶を目指して一貫して取り組んでいることを明記しておきたい。
前述したように、日本の条約参加を巡っては、相反する意見や価値観が交錯する。核兵器廃絶というゴールは共有しながらも、簡単には条約に参加しない(できない)状況がある。北東アジアには核保有国が3カ国ある。条約の批准だけでは現実は動かない。批准へのプロセス、状況づくりとセットで考えなければならない。
もちろん、“最終的には批准を目指せ”という意味で、政府に批准を求めるのは、有意義なことだ。しかし、禁止条約への「イエス」「ノー」が、全ての基準であるかのような価値観が見え隠れするのはどうだろうか。作家の佐藤優氏の視点は鋭い。
「人間は、白黒つかない、はっきりした結論の出ない状況を本能的に嫌うものだと思うんです。だからこそ、例えば社会問題について考えるときにも、一方の立場を善と捉え、反対の立場を悪と捉えて、単純な善悪二元論で考えてしまいがちです。そういう図式化・単純化は、人が本能的に陥りやすい認知バイアス(偏り)の一つでしょう」(「第三文明」2月号)
事実、そのような二元論を掲げながら、歴史を画する変革がなされた事例が、どれだけあるか。シロかクロかを突き付ければ、たとえ一部の急進的な人々の賛同を得られても、その他の多くの人々の反感を買い、理想は道半ばで頓挫してしまうのが常であろう。無責任な二元論は、かえって人々の間に分断を残すのである。
このことは、自分の職場や地域など、身近な例にも置き換えられる。仕事の理念や地域の取り組みなどを決める際、10人に聞けば、10通りの意見がある。全員が同じように答えることはないだろう。私たちはその中で、時には話し合いを通して、また時には中心者の裁量に任せながら、多様な意見の中から「ベスト」を導き出す。
慣れ親しんだ人々の間ですらそうなのだ。ましてや、無数の異なる価値観が出あう政治にあって、一つの意思決定を下す苦労の大きさは、想像を絶する。だが、政治は結果である以上、その時々に応じたベストを探り当てていくしかない。
その作業に求められるのは、ワンサイドの善悪の基準で他者を批判することではない。相反する力にもまれても「対話」という手法を手放さず、最善の道を探り当てるといった、真の責任感に裏打ちされた粘り強い行動なのである。批准への着実な取り組みが求められる。