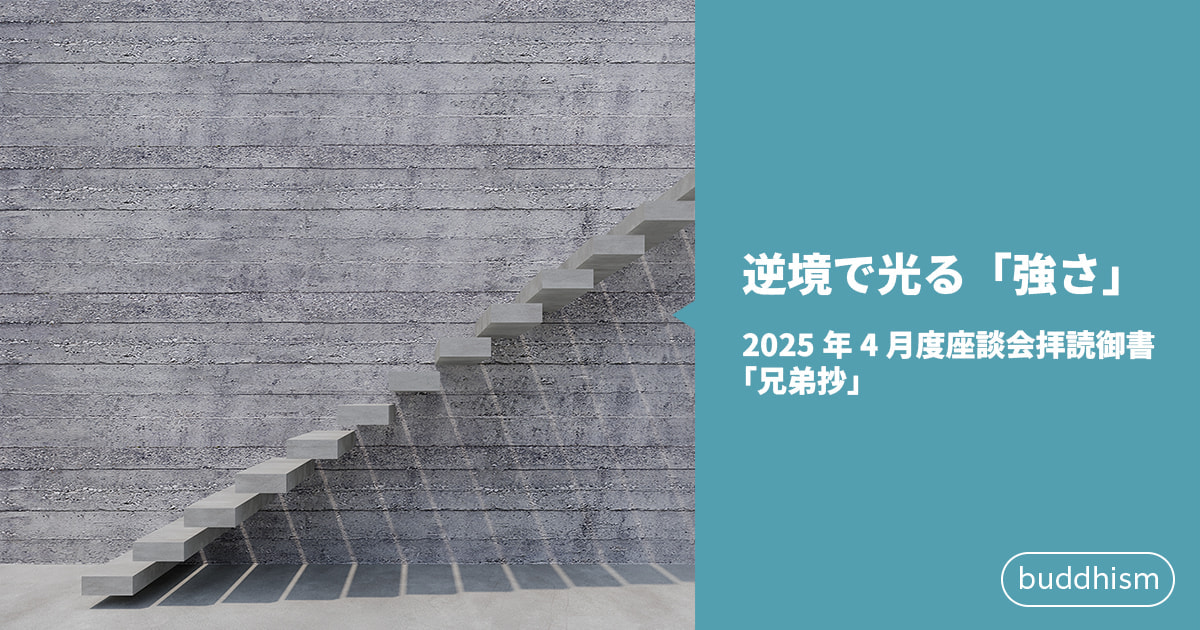強き信念が苦境を開く力に 2025年2月度座談会拝読御書「乙御前御消息」
創価学会では、毎月、全国各地で座談会という集いを開き、鎌倉時代の日蓮大聖人(1222年~1282年)が書き残された「御書」(論文や手紙など)を学び合います。機関誌の「大白蓮華」や「聖教新聞」には、その月に学ぶ「座談会拝読御書」を解説する記事が掲載されていますので、ここでは、信仰を持っていない方々にも理解しやすい視点から、青年部員が御書の内容を解説します。
一年で最も寒い時期とされる「大寒」(1月20日)は過ぎ去りましたが、まだまだ寒さが厳しい今日この頃。元々、インドア派の私は寒さが苦手。帰宅後は家にこもって暖房が効いた部屋でぬくぬくしながら、読書をするのが癒しのひとときです。
最近、『代表的日本人』という本を読みました。これは、思想家・内村鑑三が1894年、日本の誇る歴史的な人物を海外に紹介するために著したもので、西郷隆盛、上杉鷹山、二宮尊徳、中江藤樹、日蓮の5人の生涯が取り上げられています。改めて今回読んでみて、5人の共通点に気づきました。それは、試練に遭っても、一歩も退かずに立ち向かう姿勢です。
言い換えれば、「自分を信じ抜く力」「不屈の信念」を持ち続けた人といえるでしょうか。後世に名が残る偉人には、いかなる逆境にあっても信念を貫く「強い心」の持ち主が多かったように思います。
かくいう私も、仕事や家庭、人間関係の悩みに翻弄される日々が続き、「強い心」の持ち主に憧れます。今回は「乙御前御消息」の研さんを通して、何があっても揺るがない生き方のコツを学んでいきましょう。
拝読御書について
「乙御前御消息」は1275年(建治元年)8月、日蓮大聖人が身延(山梨県内)で著され、鎌倉に住んでいた乙御前の母(日妙聖人)と乙御前に送られたお手紙です。乙御前の母は、乙御前が幼い頃に夫と別れていたようです。天変地異が起こり、人々が飢えと疫病にあえぐ大変な状況下で、強盛な信心を貫きました。
1271年(文永8年)、大聖人が佐渡への流罪に処されたことを機に、多くの門下が弾圧にさらされ、退転者が相次ぎました。このような苦境の渦中にあっても、乙御前の母は微動だにすることなく、鎌倉から佐渡の大聖人の元を訪ねています。大聖人は、その求道の志を称賛され、乙御前の母に「日妙聖人」という最高の称号を贈られました。また、1274年(文永11年)の蒙古襲来後、再びの襲来の可能性に世情が騒然とするなか、乙御前の母は変わらぬ求道心で、身延の大聖人の元に足を運びました。
佐渡にしろ、身延にしろ、鎌倉から足を運ぶことは大変なことであったでしょう。大聖人は本抄で、山を越え海を越えて師匠を求め抜く乙御前の母のけなげな信心の姿勢を賛嘆され、諸天善神の加護を約束されています。
常に「いよいよ」の心で
本文
されば、妙楽大師のたまわく「必ず心の固きに仮って、神の守り則ち強し」等云々。人の心かたければ、神のまぼり必ずつよしとこそ候え。
これは御ために申すぞ。古の御心ざし申すばかりなし。それよりも今一重強盛に御志あるべし。その時はいよいよ十羅刹女の御まぼりもつよかるべしとおぼすべし。
(御書新版1689㌻13行目~16行目・御書全集1220㌻9行目~12行目)
意味
(法華経を信ずる者は諸天善神に守られる)それゆえ、(中国天台宗の)妙楽大師は「心が堅固であれば、必ず神の守りも強いのである」と言われている。その人の信心が固ければ、諸天善神の守りは必ず強い、ということです。
これは、あなたのために申し上げるのである。これまでの、あなたの信心の深さは、言い表すことができない。しかし、それよりもなお一層の強盛な信心に励んでいきなさい。その時は、ますます十羅刹女の守護も強くなると思いなさい。
語句の説明
・「十羅刹女」(じゅうらせつにょ)
法華経陀羅尼品第26で、法華経を受持する者を守ることを誓った10人の女性の羅刹。
大聖人は拝読御文の冒頭で、妙楽大師の言葉を引用しています。ここでの「心」とは「信心」であり、広く言えば、「信じ抜く力」「信念」ともいえるでしょう。強盛な信心の人には諸天善神の加護が必ず現れ、いかなる苦難にも打ち勝っていけると仰せです。
諸天善神とは、法華経の行者を守護する善神を指します。これは、何か具体的な姿を持った存在ではなく、正法を実践する人々を守る種々の働きのことです。例えば、思いがけず友人や同僚が助けになってくれる場合も、その働きの一つと捉えられます。
この諸天善神の守護の力は、私たちの信心にかかっています。他の御書にも「諸天善神の守護といっても、人の心が強いことによるということである」(新1608・全1186、通解)とあるように、その人の信心の厚薄によって、諸天善神の守護が強くも弱くもなるのです。
今回のポイントは、佐渡や身延の大聖人を訪ねるなど、すでに「心の固き」門下だった乙御前の母に対して、大聖人がさらに「なお一層の強盛な信心に励んでいきなさい」と呼びかけられている点です。これは、乙御前の母の信心が不十分だったという意味では決してありません。
過去に信心に励んできたとしても、少しでも気が緩んだり、心が退いたりしてまえば、その時点から後退が始まります。不動の境涯を築くためには、いよいよの心で前進を続ける勇気の信心が不可欠である。この日蓮仏法の要諦を、大聖人は教えられたと拝されます。
一切動じない父の姿
今回の拝読御書を通して思い出したのは、かつての父親の闘病です。私が大学1年の時、父が肺がんになり、医者から余命を宣告されました。その時に何よりも印象的だったのは、一切動じない父の姿でした。
誰しも急に「死の可能性」を告げられたら、絶望に覆われるのが常ではないでしょうか。私自身、一人息子として、“父を失うかもしれない”という不安を拭うことはできませんでした。
しかし、父は不安な様子を微塵も見せずに、「必ずこの信心で治してみせるから大丈夫だ」と気丈に振る舞い、悲嘆に沈む私を励ましてくれました。父の後ろに座って、幾度となく一緒に祈りましたが、その背中が苦難に立ち向かう「強い信仰人」として大きく見えたことは忘れられません。
時に病状が悪化することもありましたが、父は淡々としていました。一喜一憂せずに、いつもの通り御本尊に祈り、同志の元に励ましに行く。そうやって地道に信仰に励む中で、次第に父を取り巻く環境が変わっていきました。
がんの権威と呼ばれる名医に巡りあい、手術をせずに医者の提案した治療法が奏功するなど、諸天善神に守られたと実感するほど、病状は好転したのです。
「不思議ですが、がん細胞がほとんど無くなっています」。がんの宣告から約1年後、医者が驚きながら、こう告げた場面を今でも鮮明に覚えています。その後、父は寛解を果たし、70歳を超えた今でも元気に介護の仕事に従事しています。
かつて池田先生は、アメリカ・ハーバード大学での講演で、宗教を判断する要件として、「人間を強くするのか弱くするのか」との点を挙げられました。病気が治った事実はもちろんですが、何よりも「死の恐怖」に敢然と立ち向かう父の生き方を通して、「これほどまでに人間を強くするのが真の宗教なんだ」と実感できたことが、自身の財産になっています。
私の父のように、強き信念で苦境を打開してきた人たちに思いをはせると、「自分も頑張ろう!」「絶対に負けない!」との勇気が湧き上がってきます。私自身も懸命な生き方を通して、誰かに励ましを送れる存在になれるよう、「昨日より今日」「今日より明日」と挑戦の一歩を踏み出していきたいと思います。
御書のページ数は、創価学会発行の『日蓮大聖人御書全集 新版』(御書新版)、『日蓮大聖人御書全集』(御書全集)のものです。
SOKAnetの会員サポートには、教学研鑽用に以下のコンテンツがあります(「活動別」→「教学」)。どなたでも登録せずに利用できますので、ぜひご活用ください。
・御書検索(御書新版・御書全集) ・教学用語検索
・Nichiren Buddhism Library ・教学入門 ・まんが日蓮大聖人
・仏教ものがたり(動画) ・教学クイズ ・座談会御書e講義