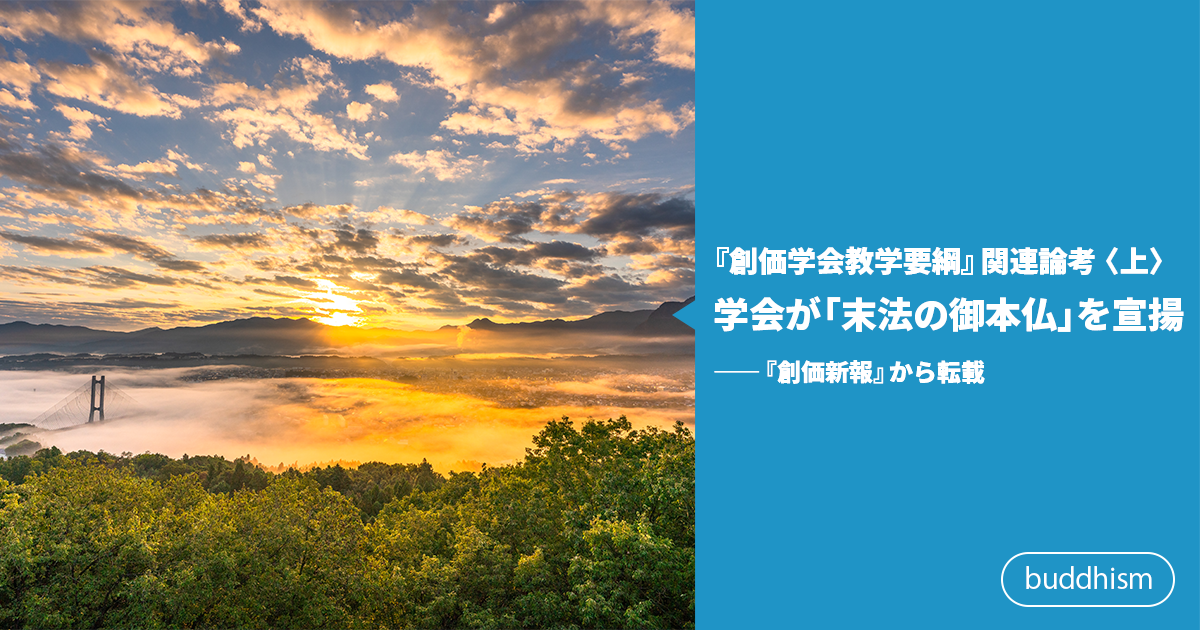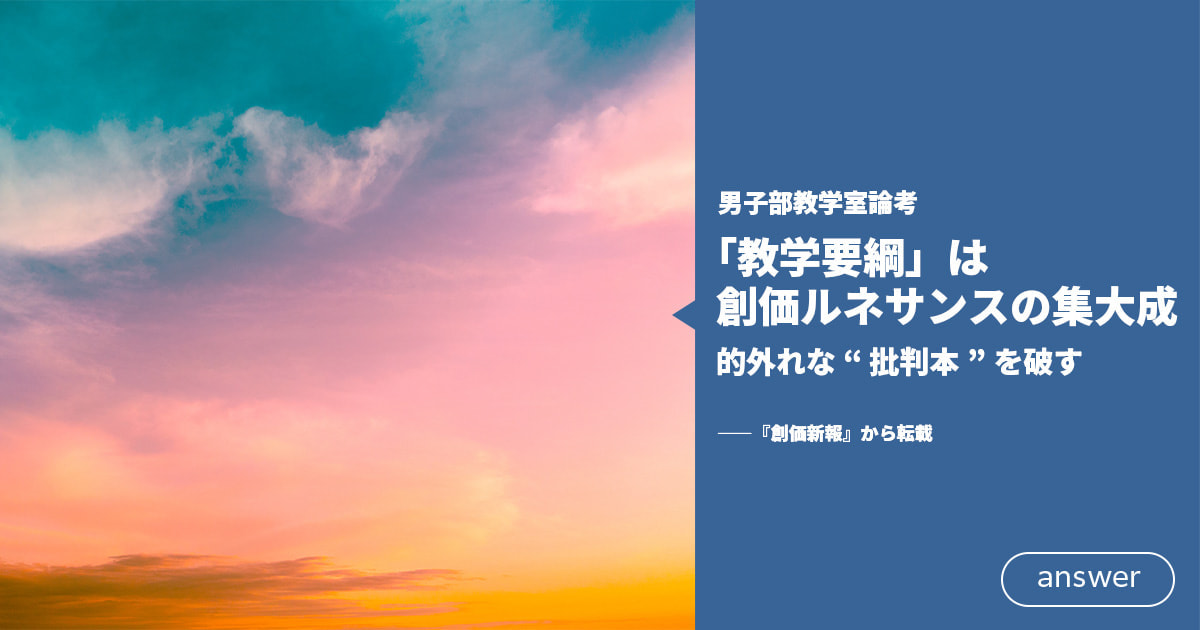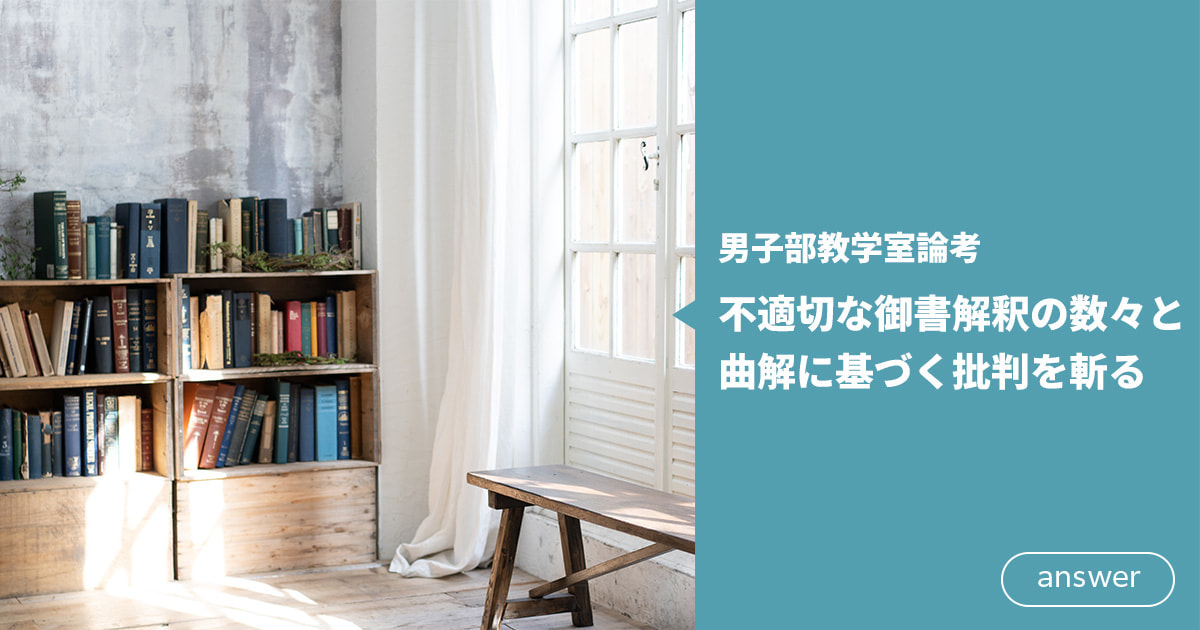『創価学会教学要綱』関連論考〈下〉 現代における「僧宝」の意義――『創価新報』から転載

創価学会では、2023年11月18日の創立記念日に際し、『創価学会教学要綱』を発刊した。日蓮大聖人の仏法が学会の手で世界へ大きく広がり、社会的な存在感が強まる中、学会がどのような宗教団体であるのかを、各国の仏教団体をはじめ宗教界、また社会に発信するために出版されたものである。ここでは、『創価学会教学要綱』に関連して、「創価新報」に3回にわたって連載された青年部の論考から〈下〉「現代における『僧宝』の意義」(2023年11月15日付)を転載する。(〈上〉学会が「末法の御本仏」を宣揚、〈中〉末法の衆生のための「三大秘法」)
仏意仏勅ゆえ学会は世界広布を実現
今月(2023年11月)18日は、世界広布の根本道場である広宣流布大誓堂完成10周年の佳節であり、創立100周年へ総仕上げの7年を出発する「創価学会創立記念日」。世界宗教へ飛躍的な発展を遂げてきた創価学会こそ、日蓮大聖人の仏法を現代に蘇らせた仏意仏勅の教団であることを、現代における「僧宝」の意義から確認する。
大乗菩薩による善知識の連帯
「未来部の 隣に座り 座談会」
これは、聖教新聞(2023年10月27日付)の連載「新・生き生き川柳」で紹介された句である。作者は103歳。二世代も三世代も超えて、老若男女が仲良く集い合う毎月の座談会は、牧口初代会長以来の創価学会の伝統として輝く。
社会学者として学会の〝現場〟に足を運ぶ東京大学大学院の開沼博准教授は昨年(2022年)、福島県の学会組織を取材した際、震災後、一早く座談会を開いたことに注目した。「集まること自体に価値を見いだす座談会を、当たり前の活動として持っていることもまた、学会の強さの根源にある仕組み」と語っている。そして、組織の特徴についてこう述べた。
「外部からは学会員といえば、皆活動に熱心で、視野が常に内部に向いて固定しているようなイメージもありますが、実際はそうではない。活動をしていなかったり、活動から離れたりする人もいる。ただ、そういう人でも人生のある瞬間にぱっと戻ってこられるような、弱く柔らかなつながりが存在し、激励が行き届く仕組みがある」(聖教新聞2022年4月8日付)
信仰は、基本として個人の営みである。その上で大乗仏教は、他者を救済する菩薩の使命に生きる。使命を共にする同志が励まし合い、自他共の幸福へまい進する連帯を構築することは、「衆生無辺誓願度」という菩薩の四弘誓願の第一を思えば、ごく自然な発露であろう。ましてや、さまざまな障魔が競い起こる法華経の実践において、時に落ち込むようなことがあろうとも、互いに支え合う善知識の存在は不可欠と言える。
日蓮大聖人が「仏になるみちは善知識にはすぎず」(御書新版1940ページ・御書全集1468ページ)と仰せの通りである。
三宝への帰依は仏法者の基本
仏教では、信仰を始める際に「三宝」に帰依する。三宝とは、仏教を構成する仏宝・法宝・僧宝であり、これらを大切に敬うことが修行実践の基本である。出家も在家も、三宝帰依に差異はない。
大聖人は、「立正安国論」で法然の邪義を破折される際、「これ破仏にあらずや。これ破法にあらずや。これ破僧にあらずや」(御書新版41ページ・御書全集30ページ)と述べ、三宝破壊であると論じられた。「報恩抄」では、三度の国主諫暁が用いられず身延に入られたことに関して、「父母の恩・師匠の恩・三宝の恩・国の恩をほうぜんがために身をやぶり命をすつれども、破れざれば、さてこそ候え」(御書新版253ページ・御書全集323ページ)と述べ、不惜身命で妙法流布に取り組まれてきたのは、三宝の恩を含む四恩に報いるためだったと記されている。
しかし、五大部・十大部をはじめとする諸御抄で、三宝を主題として取り上げ、それぞれの意味を詳しく解釈される御文は見られない。大聖人にとって、三宝の意味や、三宝を尊崇することは、仏法者として当然のことであったからであろう。創価学会も、釈尊以来の仏法の伝統を継承し、「三宝」を重んじている。
「仏宝」とは、教えを説いた仏のことである。学会では特に、末法の人々が現実に成仏できる南無妙法蓮華経の大法を弘められた、末法の御本仏たる日蓮大聖人を仏宝とする。
「法宝」とは、仏が覚知した根源の法であり、それを言葉として説いた仏の教えである。学会では特に、法華経の肝心として大聖人が覚知された南無妙法蓮華経に帰依するのであり、南無妙法蓮華経の曼荼羅御本尊を拝し、自行化他にわたる題目を唱えている。
そして、この稿で論じたいのは「僧宝」である。
大聖人は、「仏宝・法宝は必ず僧によって住す。譬えば、薪なければ火無く、大地無ければ草木生ずべからず。仏法有りといえども、僧有って習い伝えずんば、正法・像法二千年過ぎて末法へも伝わるべからず」(御書新版1217ページ・御書全集938ページ)と仰せである。
「僧」とは「集い」の意
帰依すべき「僧宝」の「僧」とは、仏の説いた法を実践する修行者の集まりである。正確には、サンスクリットの「サンガ」を音写した「僧」「僧伽」である。「サンガ」は、仏教の発祥以前から使われていた言葉で、「集団」「集会」「組合」など「集い」の意味を持ち、釈尊の時代には「共和国」の組織形態を意味する言葉であったとも言われ、「和合」とも意訳される。
法華経などさまざまな漢訳仏典において、「サンガ」を音訳した「僧」の字が、修行者一人ではなく集団を意味することは言うまでもない。三宝帰依における「僧宝」が、修行者集団を指すことも古来、不変である。
ただし、中国において、名僧、高僧のように、「僧」の字自体は次第に個々の修行者を指す意味でも用いられるようになり、さらに日本では、個人を指すことが通例となった。
一方、歴史的には、サンガの中核が出家者たちであったこともあり、単に「サンガ(僧伽)」と言う場合は、出家僧団を指すことが多いものの、サンガの本義は、「出家」ではなく、あくまで「集団」にある。そもそも、一切衆生の成仏を願った釈尊の本来の立場からすれば、サンガを出家者に限定する理由はない。ゆえに、「広く在家を含めた仏教教団全体をさすとみてもよい」(『日本国語大辞典』)とも説明されてきた。
釈尊の教団では、身分や性別などの差異に関係なく、あらゆる階層の人々が集い合い、平等に仏道修行に励んだ。初期仏典には、そうした釈尊と、出家・在家を問わずさまざまな弟子とのやりとりが、生き生きと描かれている。
「日蓮が一門」の団結を大切に
では、大聖人はどうであろうか。大聖人御自身、嵐のような迫害に襲われ、何度も活動場所から追い払われたことなどから、大聖人門下は教団として整った体制ではなかったと考えられる。その上で、出家と在家の差異については、当時として学のある立場である出家者が、文字を読むことが困難な在家者のために、大聖人のお手紙を読んで聞かせるなどの役割の違いはあったであろう。
しかし、そもそも法華経では、八歳、女性、畜身という、僧形に最も遠い竜女が即身成仏を果たすのであり、一念三千の教えに基づけば、南無妙法蓮華経の唱題行と成仏の可能性において万人は平等である。大聖人が「法華経と申すは、手に取ればその手やがて仏に成り、口に唱うればその口即ち仏なり」「この経を持つ人は、百人は百人ながら、千人は千人ながら、一人もかけず仏に成る」(御書新版1913ページ・御書全集1580ページ)と仰せの通りである。
実際に、大聖人は、難に揺るがない強盛な信心を貫いた四条金吾、池上宗仲、南条時光、富木尼、日妙聖人など、性別を問わず、在家の弟子たちも御自身と同じく「法華経の行者」と呼びたたえられている。中でも熱原の法難では、一人も退転することなく信仰を貫いた20人の農民門下に対して、「ひとえに只事にあらず」(御書新版1938ページ・御書全集1455ページ)と述べ、「法華経の行者」(同)として最大に讃嘆された。
そして、大聖人は「日蓮が一門」(御書新版1620ページ・御書全集1190ページ等)や「我が一門」(御書新版100ページ・御書全集222ページ等)など、繰り返し「一門」と述べられており、出家と在家を問わず弟子の連帯を大切にする御心がうかがえる。
ゆえに、「サンガ」の本義に照らし、また法華経の教えと、大聖人の仰せや振る舞いに基づけば、仏と法を信じて正しく実践しつつ、その教えを継承する人々の集まりこそ「僧宝」にふさわしい。
大聖人の御入滅後、大聖人の仏法を正しく継承したのは日興上人であった。そして現代において、御書と御本尊根本の実践で大聖人の仏法を発展させてきたのが創価学会である。在家仏教教団として大聖人の仏法を現代に蘇らせ、民族や文化などあらゆる差異を超えて、192カ国・地域への世界広布を現実のものにした事実こそ、民衆仏法の確立を望まれた大聖人の御本意、そして万人成仏を願う仏法の本義に則った、仏意仏勅の教団の証しにほかならない。日興上人を範として、大聖人の教えを伝持し、南無妙法蓮華経を弘める創価学会が、現代において「僧宝」の意義にかなうことは言うまでもないであろう。
破和合僧の大罪犯した日蓮正宗
仏教では、最も重い罪として「五逆罪」があり、中でも最も重いのが教団分裂の「破和合僧」の大罪である。正法を護持する人々の集いを破壊することは、人々を正法から遠ざけてしまう大悪に通じるからである。
その大罪を、現代で犯したのが日蓮正宗宗門である。大聖人の御遺命である世界広布の大願成就のために、僧俗和合を願い、宗門を外護してきた学会を、あろうことか破壊しようとしたのである。特に、法主日顕は、〝学会員のうち20万が山につけばいい〟と、「創価学会分離作戦(C作戦)」によって学会組織の分断を画策。1991年(平成3年)11月には、学会に「解散勧告書」「破門通告書」なる文書を送り付け、法主への信服随従を要求してきた。
無論、そうした宗門の主張は、御書によるまっとうな裏付けなどなく、まったくの邪義。一方、学会は、池田先生のもと御書根本・大聖人直結の信心に徹し、むしろ宗門からの「魂の独立」を果たすことで、世界広布を加速させたのである。
いよいよ創価学会が、民衆仏法としての宗教的独自性を発揮し、仏法の本義に基づいた在家仏教の特色を輝かせながら、世界宗教として一段と飛躍する時を迎えた。世界広布の最前線に立つ各国・地域の青年部が連帯して、日蓮仏法の王道を歩み、平和・文化・教育運動の大潮流を展開していきたい。
(「創価新報」2023年11月15日付)