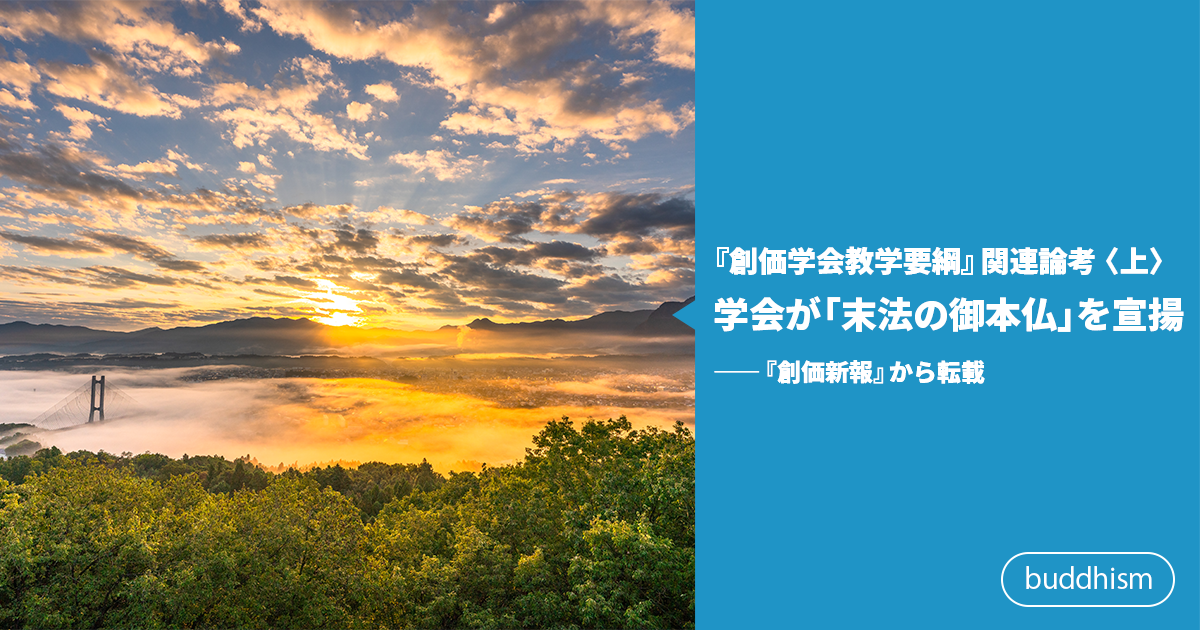男子部教学室論考 不適切な御書解釈の数々と曲解に基づく批判を斬る

須田晴夫氏が、『創価学会教学要綱』(以下『教学要綱』)を論じる本を自費出版したことに対して、「創価新報」11月号・聖教電子版に、「『教学要綱』は創価ルネサンスの集大成」と題する論考(以下「論考」)が掲載された。須田氏はこれに対し、自身のホームページにその反論を掲載した。
その内容は多岐にわたるが、ここでは、氏の御書の解釈がいかに不適切であるかを中心に、何点か指摘しておきたい。
「御書」に基づき形成されてきた創価教学
まず、大前提として、創価学会は、第2次宗門事件を経て「魂の独立」を果たして以降、池田先生を先頭に、「御書根本」「大聖人直結」の信心に立ち、「宗教のための宗教」となった日蓮正宗の独善的な教学から、「人間のための宗教」である日蓮仏法を現代に展開する、創価の宗教改革を行ってきた。「論考」でも述べられていたが、『教学要綱』は、その集大成ともいえるものだ。
須田氏の主な主張は、“『教学要綱』は日蓮を「釈迦仏の使い」と位置づけ、その下位に置いている”という批判であるが、『教学要綱』の説明を確認してみる。
一二七二年(文永九年)九月、大聖人は自身の立場について、「法華経に云わく『もし善男子・善女人、我滅度して後、能くひそかに一人のためにも、法華経の乃至一句を説かば、当に知るべし、この人は則ち如来の使いにして、如来に遣わされて、如来の事を行ず』等云々。法華経を一字一句も唱え、また人にも語り申さんものは、教主釈尊の御使いなり。しかれば、日蓮、賤しき身なれども、教主釈尊の勅宣を頂戴してこの国に来れり」(「四条金吾殿御返事(梵音声の事)」、御書一五二六〜一五二七㌻)と述べられている。ここで大聖人は、自身を「如来の使い」「教主釈尊の御使い」と位置づけ、「教主釈尊の勅宣を頂戴して」『法華経』を説いているのだと述べられている。これは、自身こそ上行菩薩の働きを行う者であるという自覚を表明されたものである。(45㌻)
御書によれば、大聖人が御自身を「如来の使い」「教主釈尊の御使い」と位置づけられており、『教学要綱』はあくまで大聖人が御書に仰せの通りのことを述べているのである。
須田氏の主張は、“『教学要綱』が日蓮を「釈迦仏の使い」と位置づけている”とするものだが、主語がすり替わってしまっている。これを誤読と言わずして、何と言えばよいのだろうか。
氏は「『教学要綱』は最後まで『日蓮は釈迦仏の使いである』という主張に固執する」と批判しているが、『教学要綱』を丁寧に読めば、大聖人御自身が“私は釈迦仏の使いである”“私こそ上行菩薩の働きを行う者である”、また「末法の教主」という自覚を持たれていたことを示す多くの御文を踏まえながら、そのうえで創価学会が釈尊ではなく日蓮大聖人を「末法の御本仏」と尊崇する意義を表明していることが分かる。『教学要綱』は、大聖人が「末法の御本仏」であることを内外に明確に説明したものであり、「大聖人は釈尊の使いである」などということを主張しているものではない。
須田氏は反論の中で、「論考」に対して「拙著の印象を貶めようとする誹謗中傷」と述べているが、須田氏の主張こそ、『教学要綱』が大聖人に反する勝手な主張をしているという印象を与える曲解とさえいえる。
目立つ御書の解釈の“粗さ”
須田氏は、“日蓮大聖人は釈尊を超越した根源仏”とするが、「論考」で指摘されていた通り、そもそも、“日蓮大聖人が釈尊を超越した根源仏である”という主張は、大聖人の御書や日興上人の著作に根拠がない。
須田氏は反論の中で、大聖人を釈尊を超越した根源仏とする根拠として、御書を幾つか挙げているが、それらはいずれも、大聖人と釈尊の優劣を述べられているものではない。
たとえば根拠として挙げている「妙密上人御消息」は、おそらくは「仏の滅後正像二千年の間は、煩悩の病軽かりければ、一代第一の良薬の妙法蓮華経の五字をば勧めざりけるか。今、末法に入りぬ。人ごとに重病有り。阿弥陀・大日・釈迦等の軽薬にては治し難し」(1708㌻)の御文のことを言っているのであろう。
通解は、「釈尊滅後、正像二千年の間は、煩悩の病も軽かったので、釈尊一代のうちの第一の良薬である法華経二十八品の肝心・南無妙法蓮華経の五字を人々に勧めなかったのであろうか。今は末法に入っている。人はそれぞれ重病にかかっている。その病は、阿弥陀如来、大日如来、また釈尊等の軽い薬では治すことは難しい」となる。ここで大聖人が仰せなのは、法華経の肝心・南無妙法蓮華経の五字という「良薬」と、阿弥陀・大日・釈尊等が説いた「軽薬」の教えの比較であり、それを説いた仏の勝劣に言及したものではない。
次に須田氏が挙げている「諫暁八幡抄」は、「天竺国をば月氏国と申す、仏の出現し給うべき名なり。扶桑国をば日本国と申す、あに聖人出で給わざらん。月は西より東に向かえり。月氏の仏法の東へ流るべき相なり。日は東より出ず。日本の仏法の月氏へかえるべき瑞相なり。月は光あきらかならず。在世はただ八年なり。日は光明、月に勝れり。五の五百歳の長き闇を照らすべき瑞相なり」(747㌻)の御文を指しているのだろうと推察する。
通解すると、「天竺国を月氏国というのは、仏が出現なさるべき国名である。扶桑国を日本国というからには、どうして聖人が出現されないはずがあるだろうか。月は最初、西の空に出て輝き、その後、東へ移動していく。それは月氏の仏法が東の方へ流布する姿を示している。太陽は東から出る。日本の仏法が月氏に還るという瑞相である。月の光は太陽ほど明らかではない。それと同じように、仏の在世の法華経の説法はただ八年である。太陽の光明は、月に勝っている。これは、五の五百歳(末法)の長い闇を照らす瑞相である」となる。
この御文も、教えを説いた人ではなく、説かれた教えに対する言及である。しかも、それは教えの勝劣に焦点があるのではない。この御文について、池田先生は、「ここでは『仏が在世に法華経を説かれたのはただ8年である』として、月の光に譬えられています。一方、末法の『長き闇』を照らす太陽もまた法華経です。日月は共に法華経の譬喩であり、込められた願いも娑婆世界の一切衆生の救済で、その心は同じです」(「大白蓮華」2015年5月号「世界を照らす太陽の仏法」)と述べている。そのうえで先生は、ここで日月の明るさの違いが提起されているのは、当時のインドや中国で仏教が失われていたことを表しているとして、「だからこそ、太陽の如く一切衆生の苦悩の闇を破る法華経の智慧の大光を、再び中国、インドの大地に還していく。仏法の人間主義の生命を蘇らせ、永遠に全民衆の心を潤していく。これを『仏法西還』というのです」と講義している。須田氏はこの御文には「日蓮が釈迦仏に勝る存在であることが示されている」と主張しているが、師の深い洞察に照らして、見当外れな解釈であるといえる。
さらに、「下山御消息」の「教主釈尊より大事なる行者」(299㌻)の御文についても、その前の部分で「今の世」と仰せの通り、つまり末法における法華経の行者の重要性を強調されたと拝される。この点について、池田先生は、「末法広宣流布を主題とした時に、いかに末法の法華経の行者が重要な存在であるのか。本抄は、(中略)末法の法華経流布の本義を述べられているのです」(「大白蓮華」2015年6月号「世界を照らす太陽の仏法」)と、末法という時に焦点を合わせて講義されている。末法における現実の衆生救済においては、歴史上の存在である釈尊が活動することはないのであるから、その意味において、「教主釈尊より大事なる行者」と述べられていると解釈すべきであろう。
そして、須田氏が「新池御書」から引用している「釈尊程の仏にやすやすと成り候なり」(2068㌻)は、この前の文に、「この経の信心と申すは、少しも私なく、経文のごとくに、人の言を用いず、法華一部に背くことなければ、仏に成り候ぞ。仏に成り候ことは別の様は候わず。南無妙法蓮華経と他事なく唱え申して候えば、天然と三十二相八十種好を備うるなり。『我がごとく等しくして異なることなし』と申して、釈尊程の仏にやすやすと成り候なり」(2067㌻~2068㌻)とあるように、大聖人に限らず、誰もが、南無妙法蓮華経と唱えることで、法華経に説かれる「如我等無異」という仏の願いのごとく、釈尊と同じように仏になれる、ということを示された御文である。日蓮大聖人が、自身を釈尊にも勝ると主張する御文ではない。
以上のように、“日蓮大聖人は釈尊を超越した根源仏である”と主張する須田氏が挙げた御文は、いずれも須田氏の主張を裏付けるものではない。それは御文の前後を読めば明瞭に分かることだろう。「読みたいように読む」とでもいうべき須田氏の御書に対する姿勢が現れているように思えてならない。
また、須田氏は、日蓮大聖人と釈尊には上下・勝劣関係があるという考えに固執していて、自費出版の本においても「(『教学要綱』は)日蓮=上行菩薩という次元にとどめ、釈迦を日蓮の上位者に置く」と批判している。このように氏は釈尊と上行菩薩は上下・勝劣関係にあるとするが、その点について、池田先生は『法華経の智慧』でこう語っている。
「『子とは地涌の菩薩なり父とは釈尊なり』(全803㌻・新1119㌻)と、大聖人は仰せになっている。師と同じ誓願、同じ責任感、すなわち師弟不二に立ち上がった弟子が『地涌の菩薩』です」
つまり、釈尊とその弟子である地涌の菩薩の関係は、上下や勝劣ではなく「不二」であることを強調している。さらに、池田先生は続けて、「そして『日蓮と同意ならば地涌の菩薩たらんか』(全1360㌻・新1791㌻)と仰せです。この同意に意味がある。日蓮大聖人の御誓願を我が誓願として、今まさに広宣流布へ進んでいる創価学会こそ、久遠の使命を担った『地涌の菩薩』の教団です。大聖人と一体の弟子の集まりなのです」と語っている。釈尊も日蓮大聖人も我々も不二であり一体である――この師匠の大確信の哲学こそ、創価教学の柱である。
なお、須田氏は「釈迦と日蓮に上下・勝劣はないというのであれば釈迦を拝んでも何ら問題ないことになってしまう」と主張しているが、創価学会においては、釈尊も日蓮大聖人も「拝む対象」ではない。氏は「本仏」と「本尊」の概念を混同しているといえる。
御金言を恣意的に利用?
須田氏が御書を恣意的に解釈している例をもう一つ挙げる。「一大秘法」という語は「曽谷入道殿許御書」に二箇所見られる。須田氏は反論の中でそのうち一箇所を取り上げて、「『一大秘法=南無妙法蓮華経』の解釈は無理」と述べている。もう一箇所の御文については全く言及がされていない。その御文は以下の通りである。
大覚世尊、寿量品を演説し、しかして後に十神力を示現して、四大菩薩に付嘱したもう。その所嘱の法は何物ぞや。法華経の中にも、広を捨てて略を取り、略を捨てて要を取る。いわゆる、妙法蓮華経の五字、名・体・宗・用・教の五重玄なり。(中略)この四大菩薩は、釈尊成道の始め寂滅道場の砌にも来らず、如来入滅の終わり抜提河の辺にも至らず。しかのみならず、霊山八年の間に、進んでは迹門序正の儀式に文殊・弥勒等の発起・影響の諸聖衆にも列ならず、退いては本門流通の座席に観音・妙音等の発誓弘経の大士にも交わらず。ただこの一大秘法を持って本の処に隠居するの後、仏の滅後正像二千年の間においていまだ一度も出現せず。詮ずるところ、仏専ら末世の時に限ってこれらの大士に付嘱せし故なり。(1399㌻)
この御文によれば、釈尊が上行菩薩をはじめとする四大菩薩に付属した法とは、法華経の中でも要である「妙法蓮華経の五字、名・体・宗・用・教の五重玄なり」と述べられている。それに続く御文に、この四大菩薩が、この一大秘法を持ったまま、正像二千年の間には出現することがなかったと述べられており、さらにこの一大秘法は「専ら末世の時に限って」、つまり末法の世のために、四大菩薩に付嘱されたとされている。この御文から、「一大秘法」とは「妙法蓮華経の五字」であるということが明確にわかる。
この仰せを踏まえて、須田氏が引用したもう一箇所の御文(「大覚世尊、仏眼をもって末法を鑑知し、この逆・謗の二罪を対治せしめんがために、一大秘法を留め置きたもう。いわゆる、法華経本門久成の釈尊、宝浄世界の多宝仏、高さ五百由旬・広さ二百五十由旬の大宝塔の中において二仏座を並べしこと、あたかも日月のごとく、十方分身の諸仏は、高さ五百由旬の宝樹の下に五由旬の師子の座を並べ敷き、衆星のごとく四百万億那由他の大地に列坐したもう。三仏の二会に充満したもうの儀式は、華厳寂場の華蔵世界にも勝れ、真言両界の千二百余尊にも超えたり」〈1397㌻〉)を読めば、末法のために留め置かれた「一大秘法」は南無妙法蓮華経であり、釈尊は、虚空会に集った聴衆に対して、この法を弘通するように諫暁したという内容であることがわかる。これに続く御文では、集っていた文殊・弥勒・智積・観世音などの諸菩薩、迦葉・舎利弗などの直弟子、梵天・帝釈などの諸天が、「我にも我にもこの経を付嘱せられよ」(1397㌻)と望んだが、釈尊は許さず、地涌の菩薩を大地から呼び出して一大秘法を託したと述べられている。
このように、御書をきちんと拝するならば、「一大秘法」とは南無妙法蓮華経であることが明らかであり、須田氏が主張する「一大秘法=曼荼羅本尊」という解釈はそれこそ「強引過ぎて無理である」。したがって、「一大秘法=南無妙法蓮華経とするのは『教学要綱』による一つの解釈に過ぎない」とする氏の批判は、何ら当たらないといえる。
『教学要綱』において、法宝を「大聖人が覚知し説き示された一大秘法である『南無妙法蓮華経』」としているのは、須田氏が言うような教義の変更ではなく、大聖人の御書に基づく本来の教義を確認したものである。
以上のように、反論に見られる須田氏の主張は、根拠の薄弱さが目立つとともに、須田氏自身の御書に向き合う姿勢に、首をかしげざるを得ない。冒頭も述べた通り、学会は、池田先生を先頭に、「魂の独立」以降、「御書根本」「大聖人直結」の根本理念に立って、本来の世界宗教にふさわしい教学を構築してきた。その師の偉大な思想闘争を、当時、教学部の幹部を務めていた須田氏は、どのように学んでいたのだろうか。